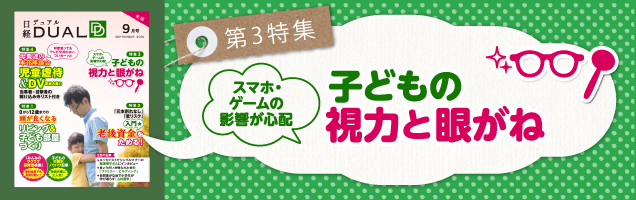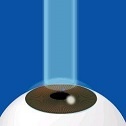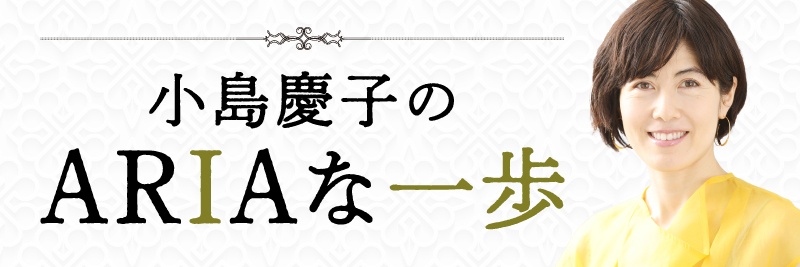8~9歳までは視力の発達期 異常を放置すると正常な視覚の発達が妨げられる
人間の目は生まれたときからしっかりと見えているわけではなく、適切な視覚刺激を受けることで、年齢とともに発達していくものです。
生まれたばかりの赤ちゃんの視力はおよそ0.01〜0.02で、物の形がぼんやりと分かる程度です。生後2~3カ月ごろになると、固視・追視(物をじっと見つめる・目で追う)という反応が見られ、両目で物を立体的に捉える機能が急速に発達します。
2歳までに0.3以上、3歳半くらいで0.5以上、4〜5歳で1.0、視覚が成熟して成人と同じレベルに達するのは8〜9歳です。
8〜9歳までの視力が発達する時期に、目の病気や、強い遠視や乱視、斜視などがあると、視力の正常な発達が妨げられ、後から治療を行っても思うように効果が上がりません。
特に0〜3歳は目の感受性が非常に高く、外からの視覚刺激によって網膜から視神経、その先の大脳の視覚野が急成長する大切な時期。「目つきがおかしい」「視線が合わない」など、目の症状に気づいたら早期に眼科を受診することが大切です。

生まれたばかりの赤ちゃんの視力はおよそ0.01~0.02。その後、視覚が徐々に発達し、成熟して成人と同じレベルに達するのは8~9歳
50人に1人の割合でおこる「弱視」は早期発見と治療が大切
視力が発達する時期に強い遠視や乱視で網膜の中心部にピントが合わず、鮮明な画像が映っていなかったり、斜視が原因で斜視の目が抑制されていると、大脳の視覚野の働きが十分に成長しないため、視力の発達が妨げられて弱視になります。弱視は近視のように眼がねで矯正しても視力が出ないのが特徴です。
弱視は子どもの50人に1人と、比較的多く見られる病気です。強い遠視や乱視、斜視が原因で起こる弱視の場合、3歳児眼科検診で見つけることができれば、小学校入学までに治療を完了することができます。目の感受性が高い時期を過ぎてしまうと、弱視治療に対する反応が悪くなり、十分な回復が見込めないことがあるので、早期発見が非常に大切です。
弱視にはおもに以下のようなタイプがあります。
弱視の重症度としては(1)>(2)>(3)>(4)の順となり、重症の弱視ほど早期発見・治療が肝心です。形態覚遮断弱視は1万人に2~3人と割合は少ないものの、強度の弱視を形成するため、0歳で発症した場合には2~3カ月以内に治療を開始する必要があります。
0歳で発症した斜視もやはり、3カ月以内に治療を開始しないと、弱視を起こしたり、両眼で物を見る機能に支障をきたします。
2歳以降に生じた斜視弱視、不同視弱視、屈折異常弱視など大部分の弱視は、3歳児眼科検診で発見されれば治療可能です。これらの弱視は子どもの50人に1人と、高い頻度で見られます。