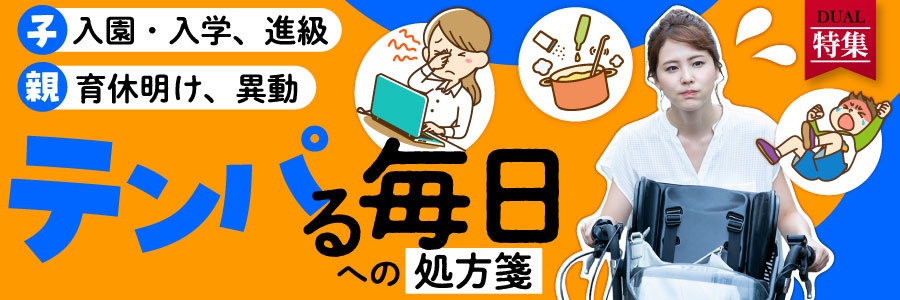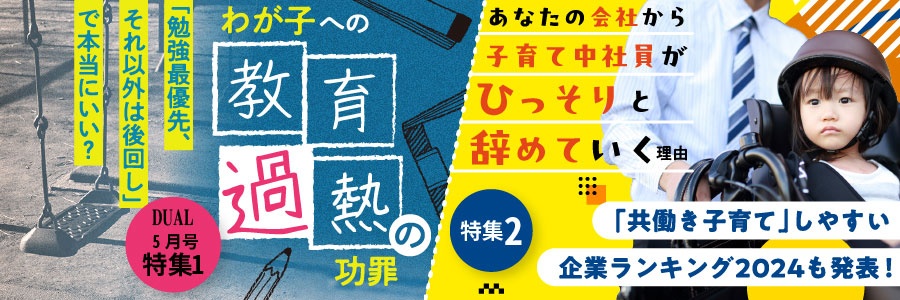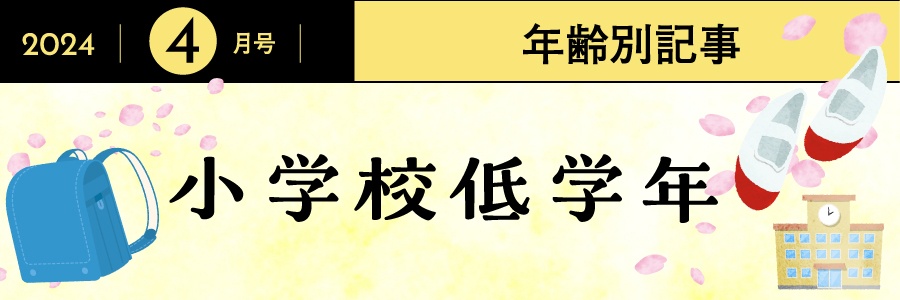- (1)不登校・行き渋りには前兆が 見逃しはこじれのもと
- (2)子の不登校タイプは、親の「子育て傾向」で変わる
- (3)不登校Q&A 共働き親「今日をどう乗り切る?」
- (4)共働き親の心配は将来のこと 不登校児はどう学ぶ? ←今回はココ
- (5)発達障害のある子が学校へ行きやすくなるヒント
- (6)中川翔子「いじめで不登校になった子のご両親へ」
「無理をしてまでいく必要はない」と考える親が増えている
フリースクール運営の草分けNPO法人 東京シューレ理事長の奥地圭子さんは最近の不登校の傾向として、小学生が増えていること、若い親世代の不登校への対応が変わってきていることを指摘します。「2000年代の初めごろまでは、小学生が不登校をすると、親は自転車に無理やり乗せたり、抱きかかえて教室まで連れて行ったりしていました。教育委員会や学校の先生も、不登校は認めず、とにかく学校復帰を目指すという方向でした。しかし、2016年に「普通教育機会確保法」が成立して、国が「不登校は問題行動ではない」という通知を出し、子どもは学校を休んでもよいこと、学校以外の場の重要性を認めた頃からは、親の対応が変わってきたと感じています」と奥地さん。
奥地さんによると、わが子が学校に行きたくないと宣言したときに、「学校が合わないなら無理やり行かせなくてもよい、もっと合う場所があるならそこでもよいのでは」と考える親が増えてきているのだそうです。「子どもが無理にでも登校しなくてはならないと考えて、長期休み明けに自殺をするという事実が広く知られてきているせいもあるでしょう。『学校が始まるのが死ぬほどつらい子は、学校を休んで図書館へいらっしゃい。』というツイッター投稿も話題になりました。親の意識として、『自殺まで追い込んだら大変、それなら休ませよう』という傾向になっている」と奥地さんは話します。
休むことは認めても、その先はどうなるのだろう。日経DUAL読者を対象としたアンケート(「共働き家庭の小学生の不登校・行き渋りに関するアンケート」。2019年7月実施。回答数38人)からは、親がそのような不安を持っている実態が浮かび上がりました。結果を次ページで詳しく紹介します。