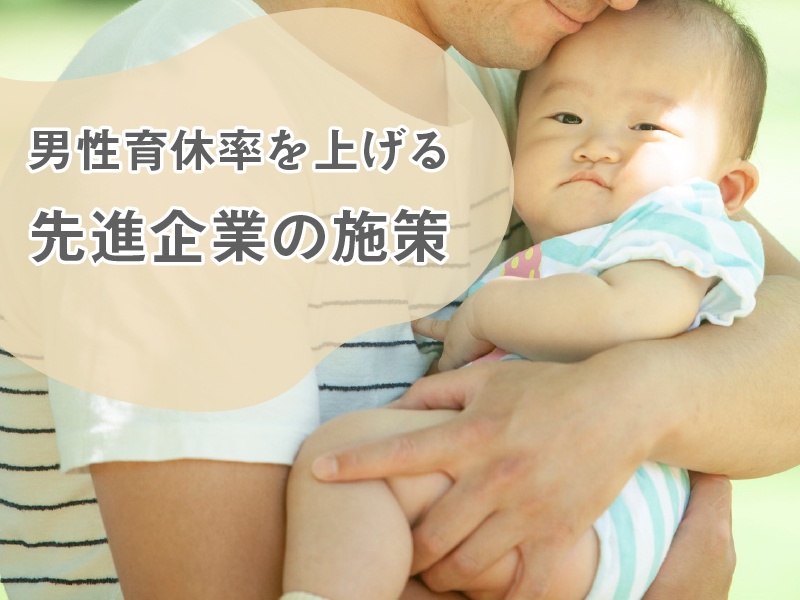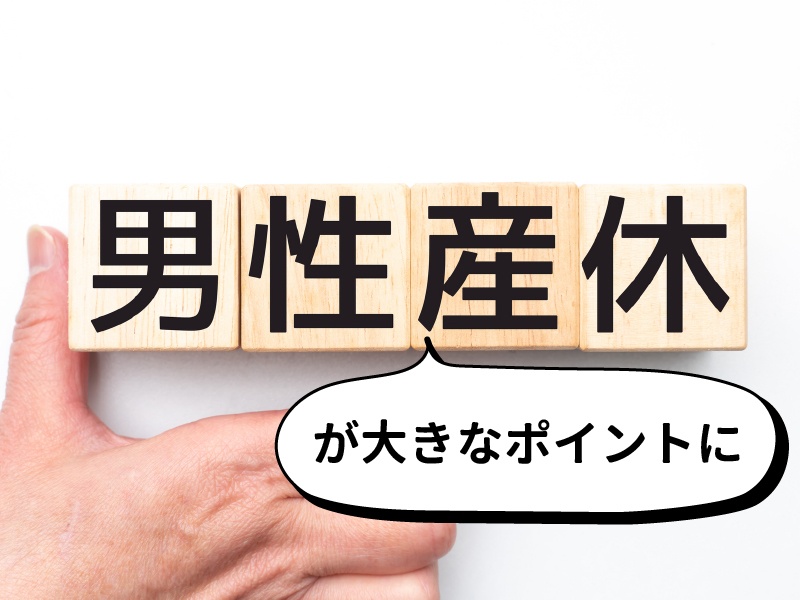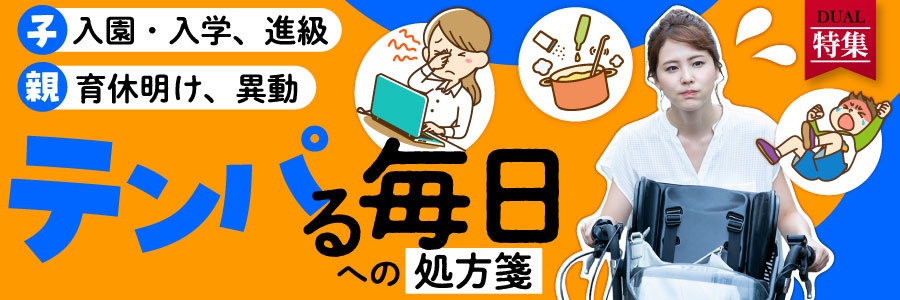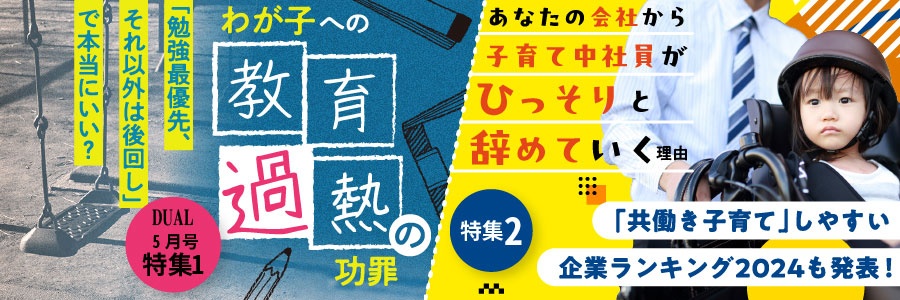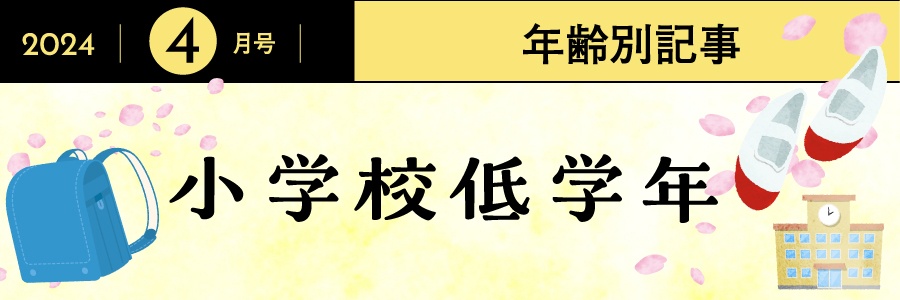- (1)男性育休「なぜ弊社で進まない?」 それぞれの悩み
- (2)どう変わる? 新・男性育休制度の解体新書
- (3)積水・メルカリ…「男性育休」先進6社の施策工夫
- (4)男性育休のハードルどう乗り越える? 3社の事例 ←今回はココ
- (5)スープストック社長の育休取得 良き前例となるため
- (6)男性育休で欠員出る現場をどう回す? 管理職の知恵
「欠員補充がされない中で、自分が休んだら周りに迷惑をかけるのではないか」「社長は育休を取るようにというが、現場の上司や同僚の意識とはギャップを感じる」。そんな気持ちで、育休取得をちゅうちょしているパパがいるかもしれません。
育休取得が当たり前の先進企業では、企業風土として、男性育休が自然に受け入れられています。そこで、男性育休取得率が高いメルカリ、大日本印刷、積水ハウスの3社の事例を紹介。育休取得のハードルを乗り越えるための、企業やパパ本人の工夫について聞きました。
■ケース1:メルカリ 会社全体で「3つの不安」を解消
People Experienceチームのマネジャーである望月達矢さんは、2017年12月に中途入社し、翌年6月の第1子誕生に合わせて1カ月の育休を取得。同社では平均して8割前後の男性社員が育休を取得しているといいます。「妻が里帰り出産し、戻ってくるタイミングに合わせて1カ月の育休を取得しました。弊社では、子どもが生まれることが分かったら、周りから当たり前のように『いつから、何カ月取りますか』と聞かれます。男女問わず、育休は子どもができたら当たり前に取得するものというカルチャーが根付いていると実感しました」(望月さん)
望月さんは、育休に入る前に、どのように引き継ぎをしたのでしょうか。