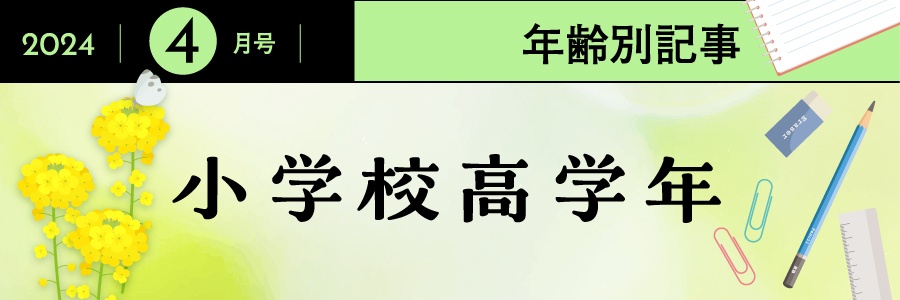おねしょに関しては、ヨメの遺伝で無縁の息子
冬の山。わたしは凍えている。このままでは凍死してしまう。何か温かいものはないか。誰かが囁く。おしっこだ、おしっこはあったかいぞ。じゅわー。ああ、何て素晴らしい解放感……そこでハッと気づく。
やってもた? おれ、またやらかした? 恐る恐る股間に手を伸ばす。
アウト。
そんなわたしの息子である以上、虎がやらかすようになるのはある種必然だと思っていた。なので、生まれた際にわたしは誓ったのだ。もし虎がやらかすようなことがあっても、絶対に怒ることはしまい、と。おねしょしたくてする人間などいないし、しちゃいけないと言われることには何の意味も抑止力もない。たぶん、そのことについての理解度ならば、わたしは日本でもトップクラスの人間だろうからだ。
ところが、虎はおねしょとはまるで無縁だった。
「おねしょ? わたし、そんなのしたことないけど」
虎をおむつから卒業させる際、自らの幼少期を思い出してだいぶ不安だったわたしを嘲笑したヨメは、「これはわたしに似たのね」と鼻高々である。確かに、年少さんの夏休みに全面的におむつとの別れを告げて以来、ただの一度もおねしょをしたことがないのだから、わたしの遺伝でないことは間違いない。普段からヨメへの感謝は欠かさないわたしだが、これはより一層感謝しておかねばなるまい。
ところが、である。
きっかけはなんだったか忘れた。ある日の朝、えらいこっちゃな剣幕でヨメが怒っている。年に一度か二度ぐらいの頻度でわたしに向けられてきた怒りの激流が、この時は息子に向けられていた。わたしですら太刀打ちできない激情の奔流である。5歳になったばかりの虎がどうこうできるはずもない。当然のことながら、ヤツは泣きだした。
すると──。
「あ、あーっ!」
激怒していたはずのヨメのすっとんきょうな声が聞こえてきた。