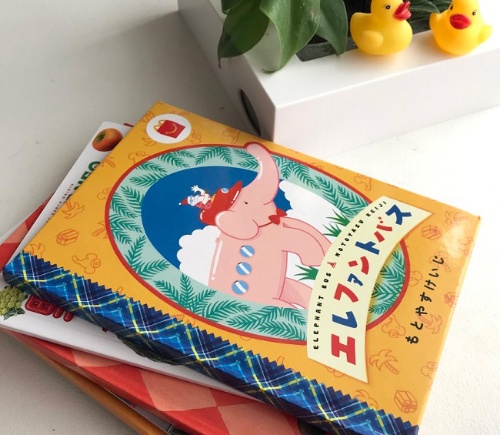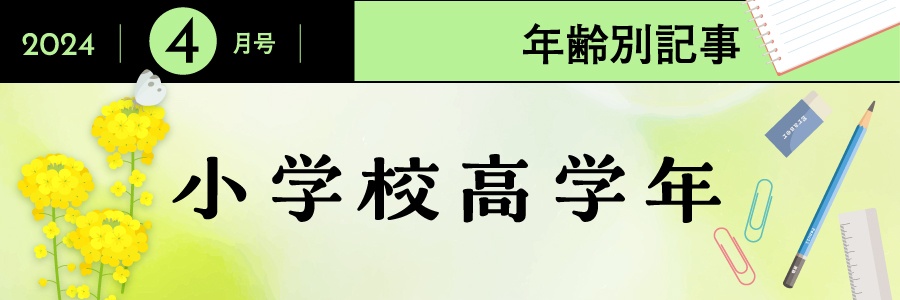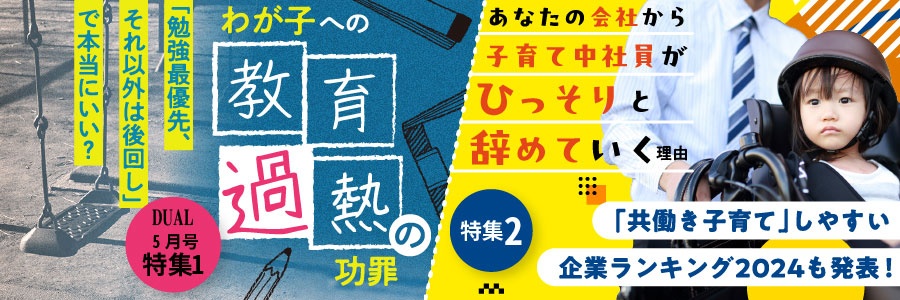寝しなの読み聞かせが"生きる力"を育む⁉
夜、本を読んであげている内に子どもが眠りに落ちていくことは多いものです。親にとっても幸せなひと時ですよね。このタイミングは、脳科学的に見て、最も読み聞かせが効果を発揮します。ヒトの脳は睡眠中に、その日の出来事、新しい表現や学んだスキルなど、情報を整理し定着する仕組みになっています。睡眠中にひらめき力も培われます。ガンガン勉強しても睡眠時間を削るとその努力は報われません。そして特に、眠る直前に得た情報は深く記憶されます。ベッドでの読み聞かせは、言語の習得と親との幸せな記憶の両者が脳に深く刻み込まれ、ポジティブな未来の種となります。
まどろむ時間はセロトニンが分泌し、誰しも心地がいい。この快感が「また読んでほしい」「本が好き」という読書に対する前向きな気持ちを育てます。本と向き合う力とは、言い換えれば「頭を使うことが嫌いじゃない」「自分で勉強しようとする」心の基礎作り。学校の勉強だけではありません。自ら考え、疑問を解決するクセが、幸せな記憶とともに育まれ、子どもの未来を決めるのです。
ひとり読書が成立するのは児童になってから
自分で読みながら想像力を巡らせる読書体験は、平均で6歳頃からできるようになります。3、4歳で音読し始めても、それは字が読めることがうれしい段階。想像力を育む読書は、まだ読み聞かせでしかできません。片や脳の「舌状回(語彙に関係する部位)」偏桃体・側坐核(快感・不快感を感じる部位)」は5歳前に発達のピークを迎えるので、幼児期の読み聞かせが非常に大切なことが分かります。
でもですね、肝心なのは幼児期の、楽しい! 好きだ! という気持ちを最優先させることです。体を動かすことも人と関わることもすべて同じ。親の下心から読み聞かせを強要すると「本が嫌い」というトラウマになりかねません。どうか、パパもママも、短かくてよいので、幸福な読み聞かせ時間をつくってあげてください。
脳科学者
 しのはら・きくのり●公立諏訪東京理科大学・工学部情報応用工学科教授。学習・運動・遊びなど多様な場面での脳活動を研究。現代の依存症問題にも取組む。「あさイチ(NHK総合)」「とくダネ!(フジテレビ)」などのテレビ番組、雑誌の監修など、多方面で活躍し著書も多い。オフィシャルサイト(「はげひげ」の脳的メモ)では興味深い最新の“脳情報”を、日々発信している。
しのはら・きくのり●公立諏訪東京理科大学・工学部情報応用工学科教授。学習・運動・遊びなど多様な場面での脳活動を研究。現代の依存症問題にも取組む。「あさイチ(NHK総合)」「とくダネ!(フジテレビ)」などのテレビ番組、雑誌の監修など、多方面で活躍し著書も多い。オフィシャルサイト(「はげひげ」の脳的メモ)では興味深い最新の“脳情報”を、日々発信している。
次に、ほんのハッピーセットの開発に「読み聞かせの余裕もなかった自身の気持ちを込めた」という、日本マクドナルドのママ社員に話を聞いてみよう。