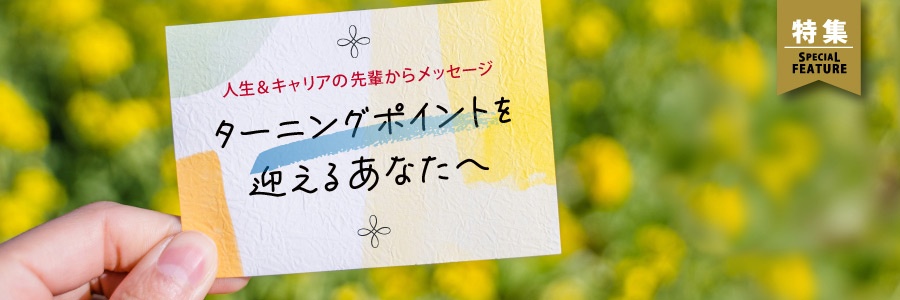『メアリと魔女の花』のスタジオポノックの代表であり、映像作品の企画から完成までを統轄するプロデューサー、西村義明さん。現在12歳の娘さんと6歳の息子さんを持つパパでもある西村さんは、スタジオジブリ在籍中から「子どものために」を信条として仕事をされてきたそうです。西村さんがアニメーションの道を選んだ理由や、アニメを通して子どもたちに伝えたいことをお聞きしました。
子どものために生きようと決めた
将来どんな仕事をしたいのか考えたのは、中学2年生のときでした。親戚に自分より小さい子がたくさんいたからか、当時から大の子ども好きで。自分も中学生の子どもでしたけどね。その頃、漠然と「子どものための仕事をしよう」と考えて、最初はゲーム・クリエーターとして、それを実現しようと思っていました。寝る間も惜しんでゲームばかりやっていた時期もあったので。
それで、大学も情報系の学科を選択しました。でも、そこで自分が志すところと、ゲームを作ることとの間に何らかの乖離があるように思えてきて。当時のゲームって結局のところ、あらかじめ用意された問題に対して、用意された答えを選択しながら進むだけだったんです。ゲームは面白いし、効率的で論理的な思考を養うには極めて有用だと今でも思っているんですが、果たしてゲームは本当に子どもたちの心の糧になるのだろうか。そんな疑問に答えを出せないでいたときに、映画の持つ力を再発見する機会があったんです。
映画って、一方通行ですよね。答えが出なかったり、そもそも正解がないテーマを、一方通行で不躾に投げかけてくる。その投げかけられた問いを僕たちは受け取って、ああでもない、こうでもないと、現実に立ち返って考える。ゲームも映画も疑似的な体験である点は変わりがないですが、選択肢も解答も用意されない現実に対峙するのに、子どもの頃の僕には映画のほうが役に立ちました。ならばそれを仕事にしたいと考えたんです。なんだかんだ言って映画が好きなだけかもしれないけれど。
結局、大学は1学期を終えるころに中途で退学していました。短絡的ですが、映画を勉強するならハリウッドだと思い込んで、2年間くらいアルバイトをしてお金をためて、ハリウッドのあるロサンゼルスに留学しました。
映画留学をしたときは、実写映画を作ろうと思っていました。それが、アニメーションを手掛けるようになったのは、こんな理由からです。例えば『火垂るの墓』と『プライベート・ライアン』は、どちらも戦争を扱った映画ですが、僕の中の戦争忌避の意識を強くしてくれたのは、『火垂るの墓』でした。高畑勲監督は反戦映画として作ったのではないと明言されていますが、子ども時代の僕に強烈な意識を植え付けたのは、作り手たちの絵を通して提示されたアニメーション映画で、写実的でリアルに描かれた実写映画ではありませんでした。子どものために映画を作るんだったら、実写よりもアニメーションなのではないか。アニメーション映画の持つ力に気づき、その作り手を志しました。そこで頭に浮かんだのがスタジオジブリだったんです。