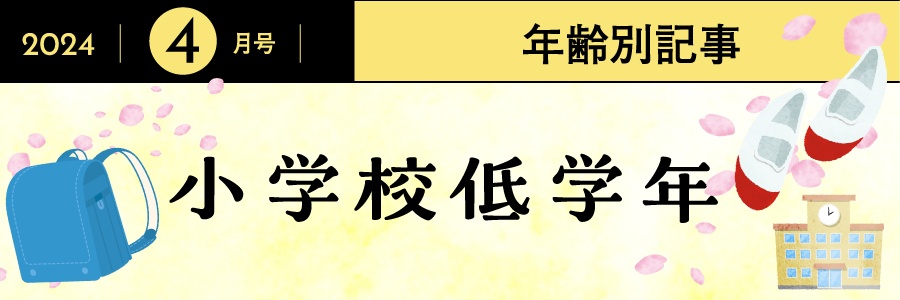1年の社会人経験での悔しさが、プロ作家に挑戦するバネに
佐藤 子どもの本を1~2冊読む読書会を、週に2回やって、作品について部員が何だかんだ討論します。創作や評論なりの冊子も作っていまして、作家志望の人も結構いました。それぞれが書いたものについて、お互い、立ち直れないくらい言いたいことを言い合いましたね(笑)。「ここの展開には無理がある」とか。遠慮して言葉を選ばないというのが、我々の中のポリシーでしたので。つらくてやめてしまった部員もいます。そこに大学1年から4年間在籍したことで、自作を厳しく批評されることへの耐性がついて、ありがたかったように思います。
―― 大学を卒業されてからは、どのようなキャリアを歩まれたのですか?
佐藤 就職はしなかったんです。私は聴力障がいがありまして、今も補聴器を両耳で使っているのですが、働くことに自信がなく、あまりバイトもしませんでした。今考えてみると、そういうハンディがあってもできる仕事は当然ありますから、自分にできる仕事をその時点でしっかり考えて就職すべきだったな、とも思いますが、親も甘かったので、「いいんじゃない。家にいて、そのうちどこか嫁に行きなさいよ」と。そういう時代でもあったんでしょうね。
ただ、友だちはみんな就職して働いていましたし、自分が積極的にその道を選んだというよりは、何かから逃げて社会人にならなかったということにものすごいコンプレックスがありました。ものを書くということについては、大学のときに色々やって神宮先生にも講評してもらったり、青山学院大学の卒業生で既に出版社に就職されている先輩方に書いたものを読んでもらったりしていたので、自分の書いているものと、プロが書くものの距離感はある程度分かっていたんです。すぐにどうこうなるものではない、と。「作家になる」ということを振りかざして青春時代を生きていたことは一度もなく、すごく好きで書いているけれど、プロになろうとなるまいとライフワークだから、ずっと一生書こう、とは思っていました。
ただ、どの段階で自分がチャレンジしていくかということに関しては、大学を出た時点では「まだ自分には力がない」、と。だから、もうちょっと書き続けながら、少し時間を掛けて頑張っていかないとならない。それと、「自分の20代をどう生きるか」ということは別の話だったので、非常に悶々としながら過ごしていました。
そうこうするうちに、一度は働いてみようかと思って、1年、普通のOLをやりました。でも、やっぱり全然ダメで。普通の条件で働くのは無理でした。電話を受けても聞き取れない。少し離れたところから指示されると聞こえない。それは、分かっていたところで言い訳にはなりませんでした。やはり障がい者という前提で、どこかに勤めたほうがよかった。健常者として働くには、当然それなりの能力が求められますよね。だからといって、何もできないというわけではなかったのですが、人より明らかに役に立たないことが分かりましたので、「これは辞めよう」と。
そして、会社に行くくらいなら、他のことは何でもできると思って、「作品を投稿してみよう」と。自分に才能があるかないかということに直面することはそれなりに怖かったですけれど、「会社に行くよりはいいや」と。社会人経験からマイナスのエネルギーを得たというか。それで親に頼んで、「1年間、時間をください。この間は何もせずに、ただひたすら書いて送ります」と告げて、7作書いて色々なところに送りました。ジャンルも問わず、児童文学から、一般小説から、何でも書きました。実は、会社員時代も会社が嫌だったので、周りに人がいないときを見計らってパソコンで作品を書いていたことも……。見つかって怒られましたけど。それぐらいOLには向いていなかったんでしょうね(笑)。
そして、その中の1作、『サマータイム』という短編でMOE童話大賞をいただいて。そこには2作送って、もう1作も佳作に入ったんです。1回のチャレンジで結果が出たのは、ものすごくラッキーだったと思いますけれど、他は全部落ちたので、実力とすれば「いくつか書いた中で、たまたま、はまれば、いいものが書けるけれども、すぐにプロとして書けるというほどの力はその時点ではなかった」のです。