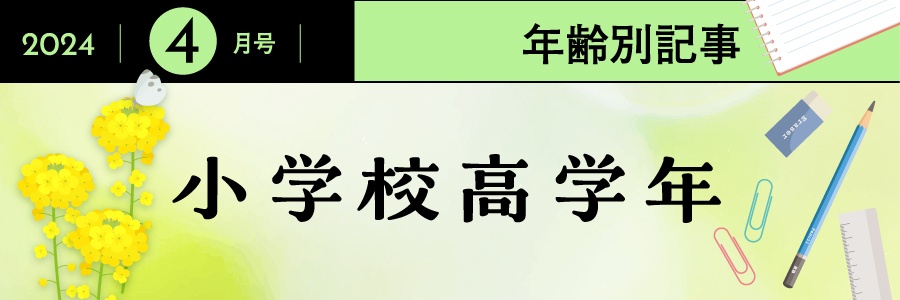続編をしたためた分厚い手紙を、従妹と交換すること2~3年
佐藤 実際は、そこまではっきりと「続編を書こう」とは意識しなかったのですが、自分たちが『わたしたちの島で』の世界にいないことがつまらないので、自分と従妹を物語の登場人物に創作をしました。ウミガラス島のすぐ近くに私と従妹だけで住んでいる島があるという設定で、もうウミガラス島の話よりも、その自分たちの島で自分たちだけで生活をすることのほうが楽しくなりました。長文の分厚い手紙にして送りました。当時はまだメールなんてありませんでしたので。従妹もすごく喜んでくれて、分厚い感想を返してくれました。そんなやり取りを2~3年はやったかな。
―― その手紙の内容だけで本ができそうですね。
佐藤 いやいや、人様にお読みいただくようなものでは全くないですよ(笑)。
―― それが佐藤さんにとって、初めての創作になったのですか?
佐藤 創作というものではありませんでしたが、“自分の創作の原点”ではあると思います。小学校3年生辺りに、訳も分からずに書いた話はありました。その後も何か物語的なものは書こうと思っていたんです。いつも原稿用紙は持っていましたし、小学校の卒業文集に「子どもの本の作家になりたい」と書いていました。私にとって、何か創作することは「よいしょ」と重い腰を上げてやること、というよりは、割と普通にやることではあったんです。従妹に送っていた手紙が何か創作である、という意識も全くなく、楽しくて仕方がない遊びという位置付けだったと思います。
私の中には「物語の中に入っていきたい」という思いが強くあるんですね。「読書」という行為が、私にとってはいまだにそうなのですが、そこから自分が何かを「学ぶ」とか「得る」とかいう意識より、異空間に行って、そこで楽しく過ごしたい、というもの。読書って、基本、自分にとってそういうものなんです。
いまだに、本を読むときは、子ども時代と変わらず、そうした読み方をしてしまいます。ですから、その異空間に“入れない”本はあまり好きじゃないんです。描写がしっかりしていない本というか、物語の中に何か矛盾があったりすると醒めてしまう。書くためには、いきなりその作品がポンとそこにあるのではなく、「なぜそれを書いたか」という必然が、書く人の人生の中にリアルなものとして、テーマや考えなど、色々あるのは確かです。でも、作中世界そのものが、いかにしっかりしていて、そこに読者が存在していられるか、ということは、子どものころから大事でしたし、今、読むときも、書くときも、一番大事にしていることですね。
リンドグレーンはすべての作品において、間違いなくその空間に読者を引き込んで、その世界にずっといさせてくれますよね。
―― 話が少し逸れますが、青学に入られたのは、作家になるための道しるべが何かあったから、なのでしょうか?
佐藤 そこは、しょうもない話なのですが、4教科の中で、理科・社会があまり得意ではなくて、国語・算数のほうができたんです。そのとき、青学は2教科受験だったので(笑)。その後も、作家の道を目指す者として、普通に早稲田の文学部を考えたのですが、受験してまで行くという気概はなかったんです。
* 次回、「作家・佐藤多佳子『執筆活動も、子どもが最優先』」も、お楽しみに!
(取材・文/日経DUAL編集部 小田舞子、撮影/鈴木愛子)