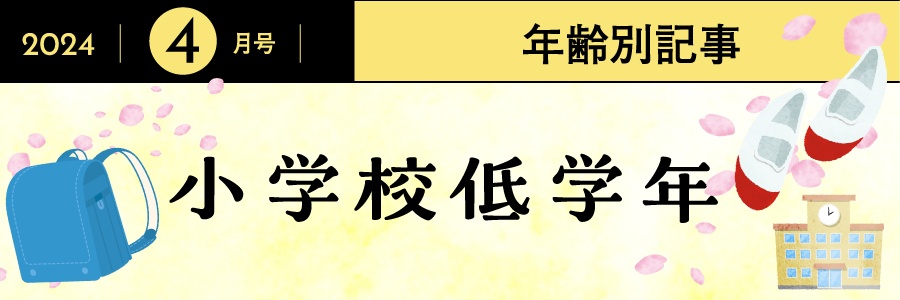周囲に好奇心を示さない子に戸惑う
小さいころの泉さんはなんでもすぐに覚える、いわゆる「できのいい子」。字を書くのも計算を覚えるのも早かったといいます。それに比べると、類さんは、何かを覚えること、学ぶことに全く関心を示しません。
「スーパーに行ったら、『これってナスって書いてあるよね』とか、『これはなんて読むの?』と聞いてくるのが子どもですよね。それはその子が言葉に興味を持っているということです。でも、類にはそういうことが全くない。
『ピーマンはどれ?』と質問することで覚えてもらおうとしても、本人に覚えようという気持ちがないんです。たとえそのとき教えても、次には『何だっけ』と忘れちゃっている。好奇心のある子は忘れたり、間違えたりしたら『悔しい』とか『恥ずかしい』という感情が自然に出てくるものですよね。そういうのが、全くないんです」
本人が興味さえ持ってくれたら、教えたいことは色々あるのに、肝心の本人が無関心。できないから、分からないから悔しいという気持ちがないから、そこをバネにして頑張ることも伝えられない。
「どうすれば興味を持ってくれるんだろう、何なら関心を示すんだろう。それが分からないから、お手上げという感じでした」
今から20年以上前、世の中でようやく発達障害という言葉が認知され始めたばかりのころのことです。泉さん自身、「発達障害」という言葉は知っていても、「うちの子がそうかもしれない、なんて、疑ってもみませんでした」。類さんが周囲に関心を示さないことも、あくまで本人の個性の一つと考えて、成長を見守っていたのです。
渡米後、親子で発達障害と判明
泉さんは、類さんが生まれたときから、どういう環境で育てていくか、将来を見据えたビジョンを持っていました。
「せっかく2つの国のバックグラウンドを持っているのだから、小学校は海外で、その後、中学は日本に戻り、高校はどちらでも自分の好きな場所で学べばいいと思っていたんです」
その計画を実現すべく、5歳の類さんを連れて、ニューヨークでスタートした母と息子の二人暮らし。日本の保育園では学生時代に引き戻されたかのような、窮屈な親同士の人間関係にへきえきとしていた泉さんにとって、米国での子育ては新たな発見の連続でした。
人と違うことも是として受け入れる多様な価値観。日本での子育てで知らないうちに心に鎧をまとっていた泉さんにも、自然と周囲の支えに感謝する気持ちが生まれていきます。そんな泉さんの変化は、類さんにも大きな影響を与えることに。今でも類さんは「周りへの感謝」をいつも感じています。
一方で、米国での生活がすべて順調だったわけではありません。小学1年生にして、留年を経験。同じころ、学校の教師の勧めもあり検査を受けたところ、発達障害と診断されます。これまで個性だと思いながら、疑問に思っていたことが、脳の機能障害が原因と言われている発達障害だと宣告されたことで、泉さんは覚悟を決めたと言います。
「発達障害ということは、そこから一生逃れられないということは覚悟しました。同時に、原因が分かったことでここからどうにかできることがあるかもしれないという意味で、ほっとした部分もありました」
「パートナーがいない」ことが吉に
パートナーも家族もいない米国で、自身も発達障害を抱えながら発達障害の子どもを育てることに、心細さを感じることもあったのではないでしょうか。
「定型発達者の人は頼れる人がそばにいてほしいと思うかもしれませんが、発達障害の私は人と折り合ったり妥協したりするのがとても苦手なんです。誰かに相談するということは、その人の意見も聞かなくてはいけないということ。意見が違えば、話し合いも必要です。
そう考えると、私が理想とする子育てをするには、自分一人のほうがよっぽどラク。思い通りに類を育てられたことは、精神的にすごく幸せなことだったと思っています」