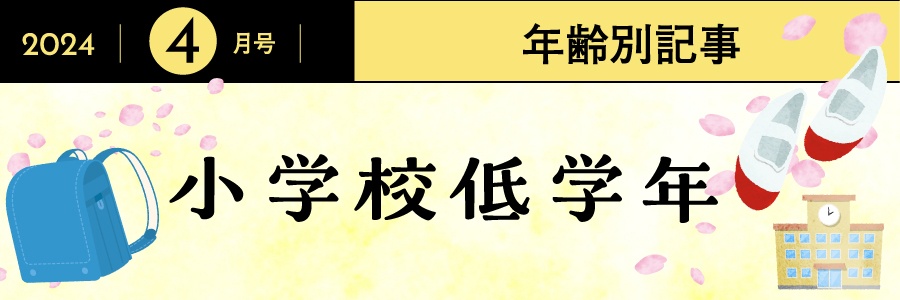診察室で見たMRI写真の胸の辺りが真っ白 「健康診断、受けてる?」
幡野 診察室に入ると自分のMRIの画像が目に飛び込んできました。素人目にも異常があることが分かるほど、背骨に大きな腫瘍があった。モノクロの透けた色の中で、異常があるところだけ真っ白に映るんです。先生も深刻なトーンになっていました。
「健康診断、受けてる?」と聞かれました。自治体がやっている健康診断って、40歳以上のところが多いですよね。僕はフリーのカメラマンで、自分の健康面は全然気にしていなかったので健康診断を受けていませんでした。「腫瘍がある」、と。背骨から発症する腫瘍というのは10万人に1人ぐらいしかないとても稀なものなので、僕の場合は他から転移している可能性がかなり高かった。「転移しているということは最後の段階。紹介状を書くから、大学病院に行って精密検査と治療を」と言われました。
―― 告知を受けて、正直どう思われましたか?
幡野 ある意味、納得しましたね。だって、それまで整形外科、内科、マッサージ、鍼など、あらゆる病院に行って皆に原因が分からないと言われて…、そして、体調は圧倒的に悪いわけで。「なるほどな」と。頭はある程度真っ白になってしまったけれど、そんなふうに思っていました。「さてこれをどうやって家族に説明しよう。参ったな」と思い、病院の駐車場で、最初に連絡したのが姉です。僕も悩んだんです。妻にすぐ電話して気を動転させて、車で事故を起こされても嫌だし、母も母で気が動転してしまいそうだし。最初にこの状態を割と受け止めてくれる人って誰かな、と思ったら、姉だったんです。
電話越しに「ちょっと俺、ガンっぽいんだよね」と告げると、姉にも最初は受け入れられず「何かの間違いじゃない?」と言われました。でも、間違いなわけがないんです。自分で分かる。姉に言えたことですごく気が楽になって、「妻とお母さんに何て言おうか」という相談もでき、「言うしかないよね」と。妻には、帰宅後、「ちょっと話がある。俺、ガンになった」と伝えました。相当ショックだったと思います。ほとんどの方がそうなのですが、最初、患者から告げられると現実逃避するんです。うちの妻も最初は「何かの間違いじゃないか」と。あまりにも衝撃が大きすぎて、状況がのみ込めていないようでした。
当時、僕は痛さのあまり、夜、横になることすらできなくなっていたので、ソファに座ったまま眠っていました。ガンが判明した夜は一睡もせずこれからどうすればいいか考えました。収入面、仕事面、治療面とか、色々考えた結果、「悩んでも、落ち込んでも、しょうがない」という考えに至りました。落ち込んで泣いても状況が良くなるわけではない。「まあ、なるようにしかならない」と。ただ、当時は余命が「3カ月」とか「6カ月」という情報が頭の中にあり、「ちょっと短いな。でも、この中でできることをすればいいかな」と考えていました。
もし「余命があと半年だ」と言われたら、働きます? 僕は「好きなことをしよう」「面倒臭いことはもうしなくていい」と思った。僕にとって好きなことというのはつまり、家族と過ごすこと。もう仕事をしている場合じゃない。その日の時点で、仕事は全部キャンセルしました。
その2日後に広告の仕事が入っていました。スタジオも押さえてあって、クライアントさんもいて、タレントさんもいて、という結構大きな仕事でした。カメラマンがドタキャンするってあり得ないことなので、関係者の皆さんに電話をして正直に「ガンになりました」と説明しました。担当者の方も、「何かの間違いでしょ?」という空気になりましたが。他の仕事もすべてドタキャンしたので、仕事はもうどっちみち入ってこないだろうな、と。余命3カ月だったら家族と遊んで過ごして思い出をつくったほうがいいんじゃないかな、って思いましたね。どこか旅行に行くでもいいし、美味しいものを食べるでもいいし、家族にはいい思い出を残したほうが確実にいいだろうな、と。
僕も18歳のときに父をガンで亡くしているんです。当時のガン治療は、今ほど進んでおらず、父はかなり治療に苦しんでいました。それが印象に残っているので、自分は家族にそういった思い出を残したくない。例えば、妻が将来子どもに僕のことを話すわけですよね。そのときに何かつらい治療話とかされても困っちゃうわけなので。子どもだってそんな話は聞きたくないだろうし。でも、そのときは体が絶不調だったので、とにかく家族と一緒にゆっくりするぐらいしか浮かばなかったかな。
―― その後すぐ、治療を始められたのでしょうか。