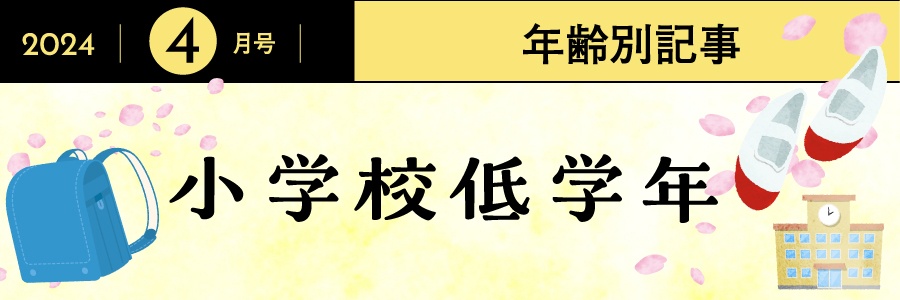海外に転勤した夫に付いていく妻は、ちまたでは「海外駐在員の妻=駐妻(ちゅうづま)」と呼ばれます。では、妻の転勤に付いていった夫は「駐夫(ちゅうおっと)」――? 共働きであれば、いつ起きるか分からないのがパートナーの転勤です。妻の米国への転勤を機に会社を休職し、自ら「駐夫」になることを選択した大手メディアの政治記者、小西一禎さん。そんな小西さんが、米国NYで駐夫&主夫生活を送りながら、日本の共働きや子育てにまつわる、あれやこれやについて考える連載です。
今回は「『主夫です』と名乗るとき心の内は…」「初めてのワンオペ10日間」「専業主婦/主夫は100%家事・育児を担うべきなのか」などについてお届けします。
英語脳のときは「主夫」を誇らしく思えるが……
私には英語を話す際、声を1オクターブ上げる習性があります。テンションを高くすることで、頭の流れを英語スイッチに切り替えているのです。これによって、日本語会話のときとは、別の人格になったような錯覚に陥ることがあります。英語という言語の特性上、どうしてもアクションは大げさになりますし、感嘆詞も多くなるのは仕方ないのかもしれません。
米国暮らしを始めてから、自らを「I am a househusband」と積極的に伝えていることは以前、紹介しました。米国人は老若男女とも好反応を見せてくれます。「悩みに悩んだ自分の選択は、この地で受け入れられている」と思うと、プライドが大いにくすぐられます。英語脳で別人格になっていることもあり、聞かれてもいないことをどんどん自ら話し、心の底からすっきりするような気持ちを味わえます。
ところが、対日本人となると若干微妙な感情が湧き起こるのです。とりわけ、同世代の男性に対して、です。彼らは、世界経済の中心地・NYに駐在するぐらいですから、企業や団体の中で、選ばれし存在なはず。家族を交えた幼稚園のクラス食事会や大学の集まりなどで自分のことを話す際、多少の恥じらいと引け目が交錯し、えも言われぬ思いが去来します。
海外版の横長名刺を持っている彼らと比べ、私は政治記者としての縦長国内名刺しかありません。日本では、政治記者である自分に誇りを持っていたのですが、アメリカ、しかもNYにいるにもかかわらず、仕事をしていないがために、マンハッタンなどで働いている彼らへの羨ましさも乗じて、ある種の劣等感を感じてしまうのです。とはいえ、会社を退職したわけではありませんし、あくまでも期間限定の駐夫、主夫です。過去のものとはいえ、自らの記号を示してくれる名刺を持っているだけ、ましなのかもしれません。
春先、大学同窓会NY支部のゴルフサークルに参加した折、初対面の先輩たちに、主夫の生活ぶりを尋ねられると、どうにもこうにも答えるのに抵抗感を覚え、強引に話題を変えて、その場をやり過ごしたことがありました。つまらないプライドを捨て去るか、一時的に脇に置き、こうした自分を克服していけば、まだまだ私自身、進化する余地はあると無理やり思い込ませています。
もし駐夫にならなかったら、連日連夜、真っ暗な自宅に戻り、子どもに会えない寂しさから、安直に酒に溺れていたでしょう。バブル崩壊後の就職氷河期に社会に出た40代後半世代は組織内での出世競争の結果が少しずつ明らかになり、第二の人生的な将来像がちらつき始めます。日々わずかながらでも昨日と違う自分を気づかせてくれる米国ライフを送れることに感謝しています。
初めての完全ワンオペ10日間が始まった
10月、とある日曜日の昼下がり。追いかけっこをする長女と長男が家中を走り回り、妻は家事の傍ら、大好きな海外のリアリティー番組に夢中です。私はといえば、食卓にて本稿を執筆。休職中のため、当然ながらオフィスはなく、自宅が疑似職場なのです。この間は、妻が兼業主婦になってくれ、ほんの一時的とはいえ、主夫業は完全休業となります。こうした機会は、もっと多ければうれしいのですが、今の立場ではなかなかそうもいきません。
9月上旬、妻が日本を含むアジア出張となり、初めてとなる完全ワンオペを経験しました。期間は実に10日間。完全休業どころか、100%主夫です。「ようやくお願いできるようになった。このタイミングで出張でも入れないと、いつまでもできないだろうから、思い切ったわ」と、どことなく上から目線の妻。
一緒に公園に遊びに行ったり、私の実家を訪れたりなど、イベント時に父子3人だけというのはありましたが、子どもたちは、これだけの期間、妻と離れたことはありません。子どもにとっても、私にとってもチャレンジでした。
娘は寝かしつけの際、初日から二晩続けて「パパなんか、大っ嫌い、ママぁ、ママぁ」と大声でわめき散らし、大粒の涙を流して、暴れまくりました。