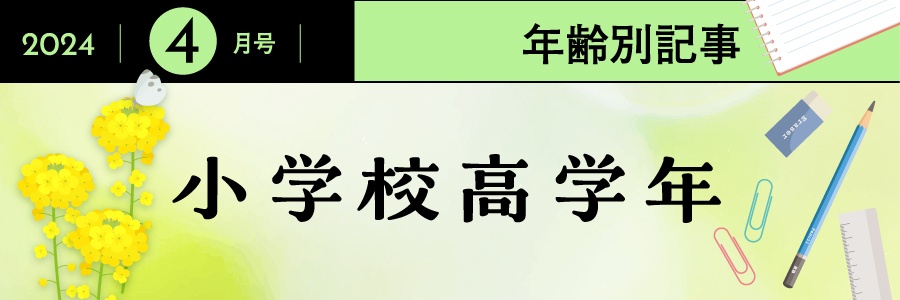「実親でなく、私たちのような里親や祖父母などでいい。乳幼児期にそれなりに愛情を受けた経験がある子は、たとえ思春期に一時荒れても、自分を大きく傷つけてしまうことはないと思います」。 里子には、3歳というごく幼い時期に迎えた長女のほか、幼いころは実親や別の里親の元で大事にされて過ごし、様々な事情で秋山家にやって来た子どもたちもいます。しかしタケシ君は、「誰か」の愛情が最も必要な人生最初の6年間を、両親の争いと虐待の中で過ごさざるを得ませんでした。
恵美子さんは「彼はある作文に『これまで人に会うのが怖かった、何かされるんじゃないかと思ってしまった』と書いていました。人への恐怖感が消えず、いつも良い子ぶって過ごしていたのでしょう。女性にもお金を出して、自分をよく見せようとしてしまうのではないでしょうか」と振り返ります。
秋山さんも苦い思いを込めて語りました。「彼は教師になりたいという希望を持っていたし、奨学金に合格するなど頭も悪くなかった。 でも結局、自己肯定感を持てなかった。私たちも応援したつもりですが、力及ばず、自立させることができませんでした」
進まぬ里親措置、「短期里親広め、気軽に託せる環境を」
厚生労働省によると、欧米では里親への委託率が50%を超える国が多い一方、日本は委託率が低迷しています。「実親の多くは、里親に託すと子どもが戻ってこなくなると考え、措置に同意してくれないのです」と三郎さんは説明します。
「しかし里親に託すなら、なるべく早い時期にしてほしい。 タケシは6歳で措置されましたが、例えばもう少し早ければ、事態は変わっていたかもしれない。子どもは6歳より3歳、3歳より0歳のほうが、愛着を形成できるのは明らかです。児相が家庭復帰を優先するのも理解はできますが、親が同居を望んだとしても、分離させたほうがいいケースもある。子どもの命と将来を優先して、決断してほしい」。三郎さんはこうも訴えました。
ただ秋山さん夫妻も60代を迎え、養育期間が10年を超えるような長期の里子を迎えるのは難しくなってきました。今後は、短期間の里子受け入れを始めようとしています。運送業を営んでいた三郎さんの両親は戦後、集団就職で上京した少年たちを雇い入れ、家に同居させて面倒を見ていました。このため三郎さんにとって、他人の少年たちが家にいるのは当たり前だったといいます。秋山夫妻に里親になるよう勧めたのも、この両親です。
秋山さん夫妻は、こうした「親代わり」のような役割が、現代も必要だと訴えます。 「実親が子育ての難しい期間、里親が子どもを預かり、事態が改善したら家庭に戻す。こうした形を広めることで、もっと気楽に短期間、私たち里親に託す環境をつくりたいのです」と、三郎さんは話しました。
では、短期里親というのは具体的に、どのように里子を育てる制度なのでしょう。次回は「3日里親」を続けている里親の経験談などをご紹介します。
(取材・写真・文/有馬知子 イメージ写真/鈴木愛子)