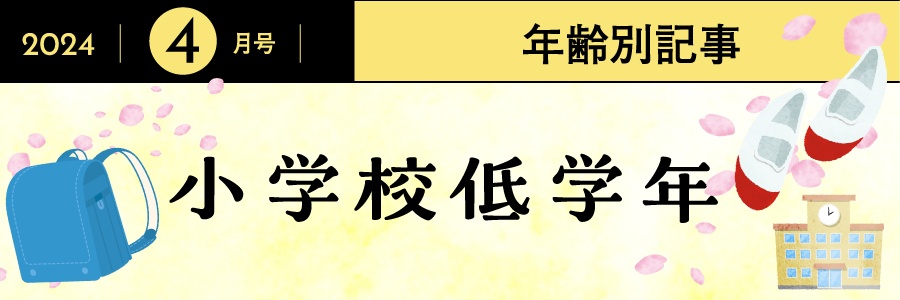閉ざされた家の中で起こることの多い児童虐待。周囲の人たちが「おかしいな」と思っても、医療関係者ですら虐待かどうかを判断するのは難しいと聞けば、自分たちだけでは発見につながらないと思うかもしれません。
しかし、多数の被虐待児を診療している松戸市立総合医療センター小児科医長の小橋孝介医師は「『何か気になる』という漠然とした不安はとても大事なサイン。見逃さないで行動を」と呼び掛けます。小橋医師が6月、市民向けに講演した内容をもとに、周りの大人たちが察知できるかもしれない「虐待のサイン」を探ってみました。
「同じ保育園に通うあの子、何だか気になる…」
「体への虐待は、こづくといった軽いものから始まり、強く叩く、傷ができる、救急搬送される、というように次第に激しくなって死に至るケースがほとんど。周囲が早いうちに気づけば、エスカレートする前に、子どもにも親にも支援の手を差し伸べられます」。
松戸市立総合医療センター小児科医長の小橋孝介医師は、早期発見の重要性を強調します。
厚生労働省の調査によると、2016年3月末までの1年間で、虐待によって死亡した子どもの人数(心中を除く)は52人。しかし小橋医師は「実際には、救急の現場で明らかに虐待であろうと推測されても、虐待死とは認定されないケースが多い」と話します。日本小児科学会が2016年に発表した調査では、虐待死は年間約350件と推計され、ほぼ1日に1人が亡くなった計算になります。
小橋医師が勤務する松戸市立総合医療センターの「家族支援チーム」は2009年に設立され、2017年には300件以上の虐待案件に対応しました。しかし、今年は6月までの半年間で、既に300件を超えたといいます。
小橋医師が講演で話したのは、医療関係者向けの虐待対応啓発プログラム「BEAMS」の、ステージ1と呼ばれる部分です。BEAMSは3段階に分かれており、ステージ1は虐待の定義や根幹となる考え方を学ぶことで、虐待を早く見つけて支援機関につなげることが目的です。ステージ2以降は医療的な対応など、より専門的な知識に進みます。
「人間は何かを疑うと、『そんなはずはない。親はいい人そうだし、子どもも元気そうだ』などと、それを打ち消す情報を集めようとしたがります。でも、1つでも心配な要素があるなら、行動を起こすことがとても大切です」。
これは虐待? 「パターン痕」に注意
では、どんなことが虐待のサインなのでしょう? 小橋医師は、例えばあざややけどの形などからも、ある程度の推察はできると言います。特に、「パターン痕」と呼ばれる特定可能な傷跡は危険なサイン。虐待を受けた子どもの57%に、少なくとも1つ以上のパターン痕が存在しました。