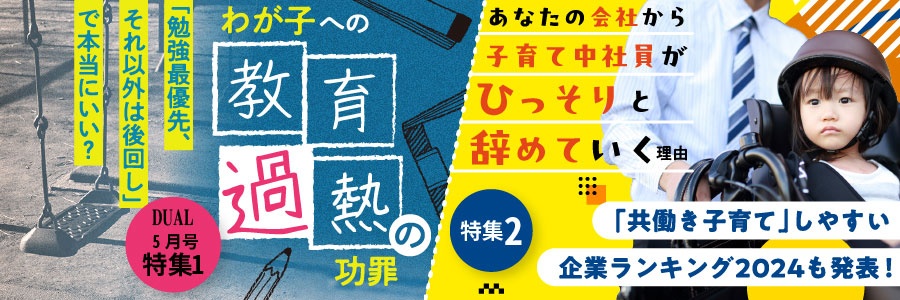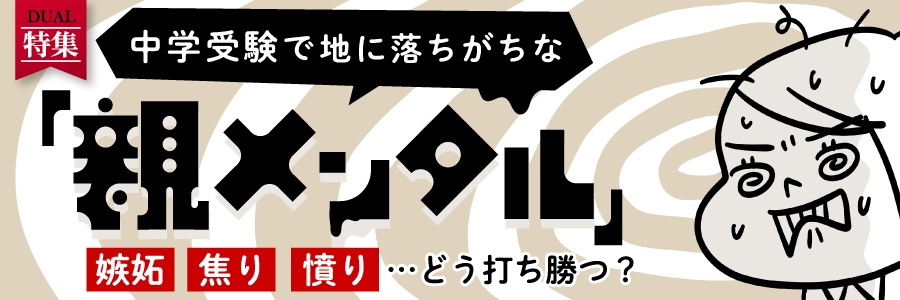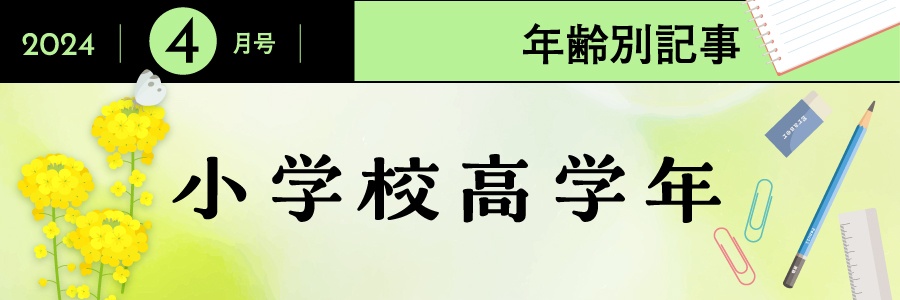ハンターになって、水辺の草むらに目を凝らしてみる
身近なところで外来生物が問題になっていること、それを解決するためにはどうしたらいいかということ。こうしたことについて考えられるように育った子と、何も学ばずに育った子では、環境に対する行動が大きく変わります。
人間が生きていくうえで、生き物との関わりは避けて通れません。だから、生き物についての専門的な仕事に就いてほしいということではなく、むしろ学んだ子がいろんな分野に進んでほしいと思っています。例えば靴を作るという仕事を見たときに、東南アジアの一部の地域では、まだ廃材や廃液を川に捨てるといったことが行われています。でも、それが生物にどんな影響を与えるかという視点があれば、いざというときに環境に配慮した行動が取れるようになりますよね。
生き物は、探せばいろんなところに隠れています。外敵に見つからないようにしているので意外と見つけるのは大変ですが、ハンターになった気分で、身近な公園に出かけて水辺の草むらなどに目を凝らしてみてください。一見何もいないと素通りしてしまう池でも、よく見るとカメが顔を出していたりしますよ。
最近は都市型の公園だと、「こんな生き物が見られますよ」とか、「こんなものがいたら困るので教えてください」といった案内の看板があったりします。また、地域のボランティアや、環境指導員といって、行政が開催するセミナーで専門家から学んだ方もいると思いますので、分からないことがあったらどんどん聞いてみてください。
野外に放されてしまった外来種は一匹残らず捕獲しないと、問題は解決しません。みんなの目で水辺を見ることで、変な魚がいたら行政に連絡してもらえるし、カメや熱帯魚を放そうとする人がいたら止めることもできる。誰でも環境改善に貢献することができます。大人も子どもも、地域のみんなが関心を持ち、解決するものだという意識を持ってもらえたらいいですね。
(取材・構成/日経DUAL編集部 谷口絵美)
 静岡大学教育学部講師。1979年静岡県生まれ。静岡大学大学院教育学研究科修士課程修了後、岐阜大学大学院連合農学研究科博士課程修了。博士(農学)。カメやトカゲの保全生態学的研究を行いながら、学校や地域社会において環境教育活動を行う。また、未知の生物を求めて世界中のジャングルや砂漠、荒野へ足を運び、その姿は「クレイジージャーニー」(TBS)で「爬虫類ハンター」として紹介されている。外来生物が生態系に及ぼす影響についての研究にも取り組み、「池の水ぜんぶ抜く」(テレビ東京)に専門家として参加するなど幅広く活動中。
静岡大学教育学部講師。1979年静岡県生まれ。静岡大学大学院教育学研究科修士課程修了後、岐阜大学大学院連合農学研究科博士課程修了。博士(農学)。カメやトカゲの保全生態学的研究を行いながら、学校や地域社会において環境教育活動を行う。また、未知の生物を求めて世界中のジャングルや砂漠、荒野へ足を運び、その姿は「クレイジージャーニー」(TBS)で「爬虫類ハンター」として紹介されている。外来生物が生態系に及ぼす影響についての研究にも取り組み、「池の水ぜんぶ抜く」(テレビ東京)に専門家として参加するなど幅広く活動中。