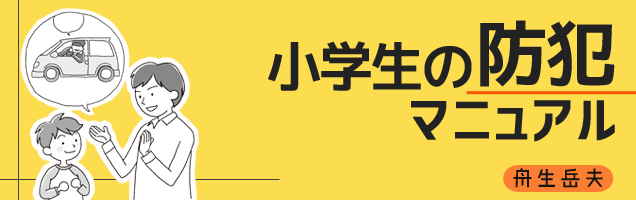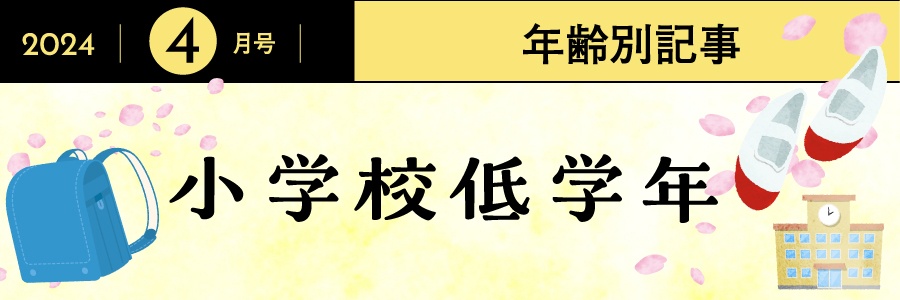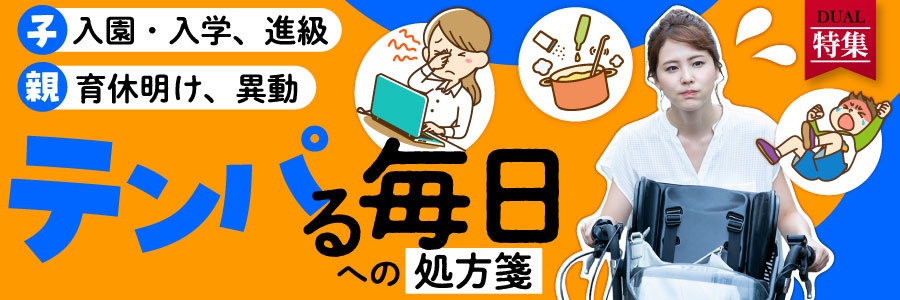習い事や友だちと一緒に子どもたちだけで遊びに行くといった機会が増え、親の目が届かない行動範囲が広がっていくと、「そろそろうちの子も、ケータイデビューかな?」と考える方も多いと思います。小学校入学を機に与えるという家庭も増えているようです。
実際、警視庁の調査によると、小学生の携帯電話・スマートフォン(スマホ)の所有率は、2015年時点で5割に上っています。特に最近ではガラケーではなくスマホを持つ大人が増えていますから、小学生が初めて持つ電話もスマホの割合が増えていくでしょう。
ここで改めて注意しておかなければいけないのは、子どもに持たせるケータイ、特にスマホの危険性です。
ケータイやスマホを初期設定のまま渡していない?
スマホというものは、電話というより、電話機能付き超高性能パソコン。本来であれば「いつでもどこでも連絡を取れる」という、子どもの防犯に役立つツールであるはずですが、使い方次第ではネットの世界特有の「サイバー犯罪」に巻き込まれるリスクを高めてしまうのです。
法規制によりあからさまな「出会い系サイト」による犯罪被害は減少していますが、それに代わって増えているのが「コミュニティサイト」や「ID交換掲示板」を通じての被害。LINE、ツイッター、インスタグラムといったSNSで情報の発信や交換をしたり、そのためのIDを教え合う掲示板サイトの利用によって、見ず知らずの人と知り合うきっかけは簡単に作れます。顔が見えない世界では、中年男性が小学生の女の子になりきって、子どもの個人情報を聞き出すこともたやすくできてしまうのです。
こういった犯罪リスクを減らすためにまず心がけたいのは「ケータイやスマホは、初期設定のまま子どもに渡してはいけない」という大原則です。
有害なサイトにアクセスできないよう制限するフィルタリングの機能を活用して、性や喫煙などの情報に子どもが簡単に触れない環境づくりをすることが大事です。
「キッズケータイとして売られているものを渡せば、大丈夫でしょ?」と油断しがちですが、どのような制限になっているかは、各社の基準によって違います。契約する段階で店頭で聞き、設定の変更方法や解除の方法(あまりに簡単すぎると子どもが変えることができてしまい、意味がない場合も)を確認しておきましょう。一番危ないのは、親が使っていたケータイやスマホを「買い替えるから、これ使ってもいいよ」と渡すパターン。親が閲覧していたサイトにそのままアクセスできるようになっていたり、クレジットカード決済の登録が残ったままになったりしていないか、必ず確認してください。
最近では、子どものケータイ利用の管理を目的としたフィルタリング機能や利用状況のチェック、位置情報の検索に特化したソフトなども出てきているので活用してみるのもおすすめです。