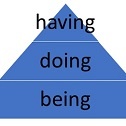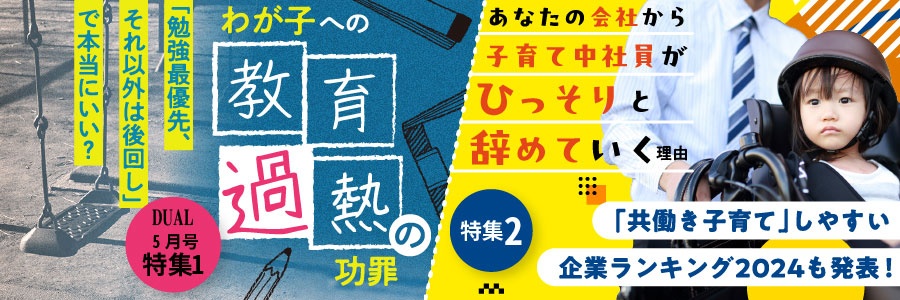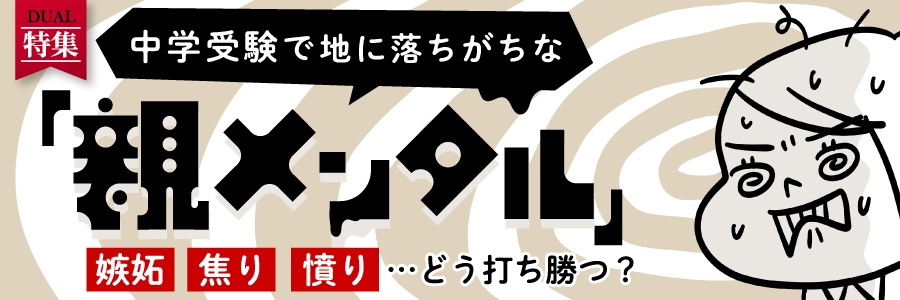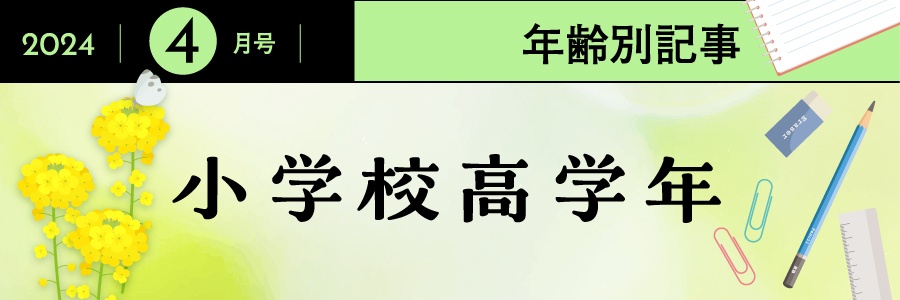「ギャングエイジ」の不安は、「つながり力」へとポジティブ変換
小学校中学年というと、皆さんはどのようなイメージを持たれるでしょうか? 一人で登下校することも集団生活で学ぶことも、親視点では「当たり前」の毎日となっていく中、子どもたちはますます自分自身のアイデンティティーの芽をぐんぐんと伸ばしていきます。
同時に、自己が次第に確立していきながら、「やりたいコト、やりたくないコト」がはっきりと出てきます。いわゆる“やる気スイッチ”がONになるのですが、やりたくないことにはスイッチがOFFになりやすくなる時期でもあります。
その中で3・4年生は特に、「ギャングエイジ」と表現されることが多い学年です。思春期前の明るい子どもたちには似合わない「ギャング」という言葉。いったいどこから来るのでしょうか?
それは、学校生活に次第に慣れていき、気の合う友達とワイワイガヤガヤ、集まって「仲間」を作っていくことによるものです。クラス替えによって、友達や環境の変化にもまれて戸惑う子も中にはいますが、そうした次第に広がる仲間同士の絆が、良い行動だけでなく一人ではやらなかったような冒険もつい引き起こしてしまう。それまで個々でしていたちょっとしたいたずらが、仲間との相乗効果により「ギャング」のような社会行動へと変換されることがあるのが、ギャングエイジの特徴です。
皆さんも記憶にないでしょうか? 「おい! ピンポンダッシュだー」なんて、ランドセルを背負った子どもたちが走っていく姿を。「赤信号みんなで渡れば怖くない」と昔の流行語にあるように、仲間と徒党を組んでちょっと悪いことをしたくなる例の一つです。今は赤信号だけでなく青信号だって気を付けて歩かなければいけないくらいの慎重さが、時には欲しいくらいですが、アイデンティティーの確立や旺盛な好奇心に従って、発達の中で「やんちゃ」な部分が顔を出していきます。
そのギャングないたずらも多少のことならばある意味での「子どもらしさ」になると思いますが、その中でも「いい」「悪い」の判断はしっかりと持ってもらいたいものです。