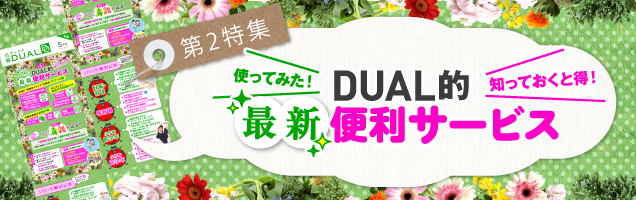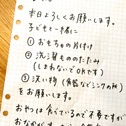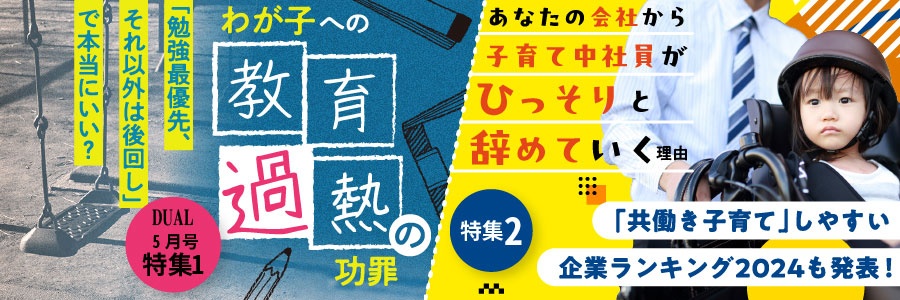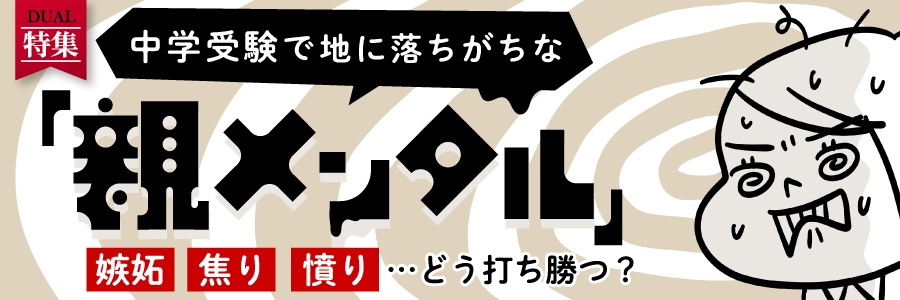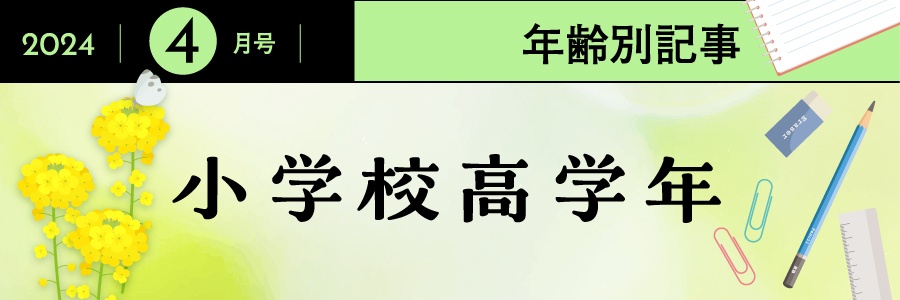家庭学習における、紙とタブレットのメリットとは?
文部科学省が、2020年代に児童・生徒1人1台のコンピューター環境を整備することを目標に、ICT(情報通信技術)教育を進めています。既に学校現場ではデジタル教材が導入され、塾でもWebを使った学習が始まるなど、教育のデジタル化は確実に進んでいます。
家庭向けの通信教育業界でも、ここ数年で小学生向けのタブレット教材が続々とリリース。2012年12月にジャストシステムが「スマイルゼミ」を、2014年4月にベネッセコーポレーションが「チャレンジタッチ」を、2016年4月にZ会が「タブレットコース」を開講しています。その他にも、様々な企業によるタブレット教材や専用アプリ教材などが登場しています。
まさに注目の高まるタブレット教材。もしかしたら、これからは紙の教材を凌駕していくのでしょうか。『タブレットは紙に勝てるのか~タブレット時代の教育』(ジャムハウス)などの著書がある、日本教育情報化振興会会長、東京工業大学名誉教授の赤堀侃司さんは、「紙の良さ、タブレットの良さはそれぞれ。ブレンドすることが大切」と言います。
「紙の良さ、タブレットの良さは、下記にある私たちの調査データでも示されるように異なります。子どもの学習においては、“紙だけ”“タブレットだけ”などと偏らずに、両方を取り入れることでそれぞれのメリットを得られ、学習効果が上がるのではと考えています」(赤堀さん)
紙の教材、タブレット教材、それぞれのメリットは何でしょう? 赤堀さんらの調査によると、タブレット教材は「写真の中の対象物が数えやすい」「写真の全体を思い出しやすい」「もう一度やってみたい」「退屈しにくい」といった特長があることが分かりました。

赤堀さんの研究資料から。中学生と大学生を対象に紙、PC、iPad3つのメディアで60名に実験を行った結果。紙とタブレット教材の効果に違いがあることが分かります
なるほど、紙とタブレットなど、学習するツールを“ブレンド”する必要性がよく分かります。
実力がアップしたのは、紙ではなくタブレットだった理由
さらに、タブレット教材の意外なメリットが明らかになりました。自動的に採点されるので、「×」になったときに親に叱られることがないということです。
「小学6年生の子どもに、タブレットに似た機械を自宅に持ち帰らせて夏休みに1カ月間の実験を行いました。タブレットで勉強するグループと紙のテキストで勉強するグループに分け、紙のグループには『もし分からなかったら家の人に聞きなさい』と指示し、タブレットのほうには『分からなくても、家の人には聞いてはいけません』と厳しいルールを与えました。
1カ月後の学習効果の伸び率は、どちらが高かったと思いますか? 当然、家の人に聞いたほうが伸び率が高いと思うかもしれません。タブレットでは、間違えた理由をわざわざ教えてくれませんし、自分で考えなくてはならないからです。
ところが実際は、伸び率が高いのはタブレットのグループだったのです」(赤堀さん)