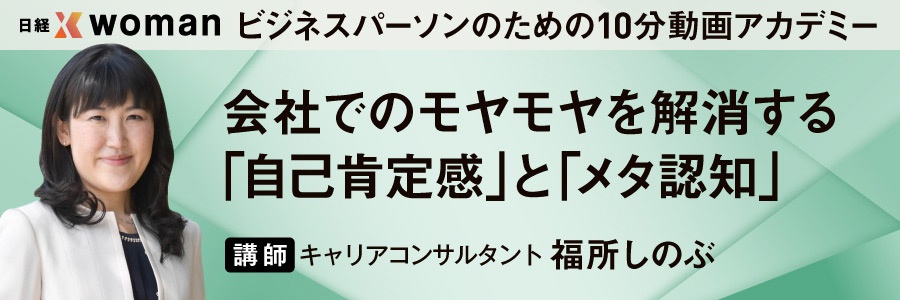テレビ局というマッチョな組織では、女性は少数派。なかでも若い女性アナウンサーには、男性や年長者が納得する「女子らしさ」が求められる。苦痛だったけれど、「若くて可愛い女の子」だったからこそ、駆け出しの頃からゴールデン番組に出演し、大物司会者とも親しく仕事ができたのも確かだ。しんどいけどオイシイな、と思ったことは何度もある。でもそれが健全だと思ったことは一度もなかった。だから結局は辞めたのだけれど、しかし男性が多数派の職場で男性と同じ待遇で働く女性なら、踏み絵を踏んだ者に与えられる歪んだ特権に気づいたことがあるだろう。たとえ利用したことはなくても。
「女性をもっと増やそう」と本気で言えるか
それを手放せるかどうかが、いま問われているのだと思う。女性の管理職を増やそう、という掛け声の陰で「それじゃ私の希少性がなくなっちゃう」と苦い顔をしている女性は確実にいる。そうでなくても「ライバルが増えるのか」「自分は埋没してしまうかも」と不安になっている人もいるだろう。
そこをぐっとこらえて「いいよ、もっと女性を増やそうよ」と言えるかは、その人がそれまで何を自分の資本と考えてキャリアを築いてきたかによる。資本を「武器」と言い換えてもいい。
マッチョな男性が優位となる社会で、その価値観を内面化し、男性の望む女性像を忠実に体現することで特権を得て他の女性との差別化を図るという、女子アナ的な、今どき風に言えば「イヴァンカ女子」的な生き方をしてきた人なら、イヴァンカは一人でいい、と考えるだろう。いつまでも蜜を舐めていたければ、他の蝶々なんか追い払ってほしいはずだ。一度手にした花を手放すのは至難の技。後味が苦いと気づくのには、時間がかかる。蜜には限りがあるということにも。
一方で、女子アナ的なやり方を否定し、自分は女を捨てて実力で今の座を手にしたと自負している女性の胸の内に、いつのまにか「大抵の女は無能だ」という女性蔑視が育っていることもある。「自分は特別で、他の女とは違う」と考えている点では、両者は同じなのだ。比較対象が同性に限られるところに、自分が女性であることを強烈に意識せざるを得なかったしんどさが滲んでいる。
女子アナついでに言えば、女性アナウンサーの意見が一致するのは「男性アナは嫉妬深い」ということだ。