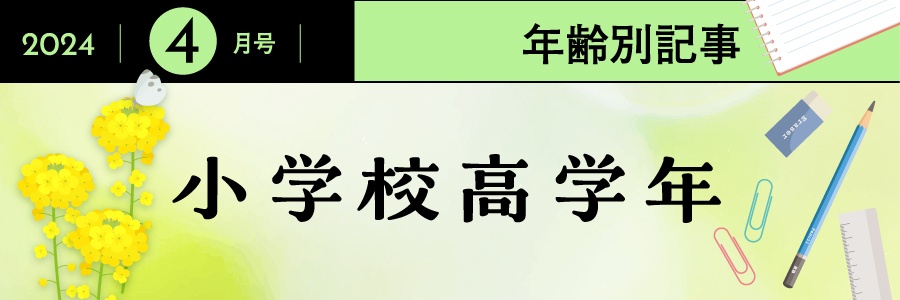むく、ありがとう
どこかケガでもしたのか。それこそ、まくらに噛まれでもしたのか。咄嗟にそう思ってしまったぐらいの、火がついたような泣きっ振りだった。
「どうしたの、虎ちゃん、どこか痛いの?」ヨメが慌てて駆け寄る。激しく首を振るばかりの虎。どうしたんだろう、と思いながらも、いつものような瞬発力で反応できない自分がいる。虎の世話をヨメに丸投げし、コンビニ限定、さくらんぼ味のチューハイを口に含む。ちょっと甘ったるいけれど、今日に限っては悪くない。なんとなく、そんなことを考えていたら――。
「むくともう遊べないの、嫌なの」
我に返った。というか、一気に引き戻された。理由はわからないが、ついさっきまで死というものをまるで理解できなかった4歳児の胸に、突如として今目の前にある出来事の意味が、鋭い刃となって突き刺さったらしい。
「幼稚園のお友達も、先生も、道行く人も、いつか死んじゃうんでしょ? だったら悲しいの」
道行く人! あまりにも意表をつくボキャブラリーにびっくりしながら、ヨメが慰める。抱きしめる。それでも、虎の嗚咽は止まらない。じゃあ、むくを撫でてあげよっか。そう振ってみても、泣き止まない。
涙と、笑いが、この日一番の勢いで込み上げてきた。
虎は、理解した。命には終わりがあるということを、この世に死というものがあることを、なぜか、突然理解した。病院では無邪気にむくの耳たぶをいじっていた4歳児は、母親がどれだけうながしても触ろうとしなくなった。
ありがとう、むく。
病院でお前の耳たぶを虎がいじっていた時、俺はちょっと思ったんだ。まだ4歳だから仕方がないけれど、でも、もし命というものに生まれつき無頓着な人間だったらどうしよう、と。ちょっと笑いながら、ちょっとだけ、ほんのちょっとだけひんやりしたものも感じてたんだ。
でも、大丈夫だった。
お前がことあるごとに顔を舐めていた赤ちゃんは、お前の死に身悶えせんばかりに泣きじゃくる4歳に成長してた。
虎は、モンスターなんかじゃなかった。