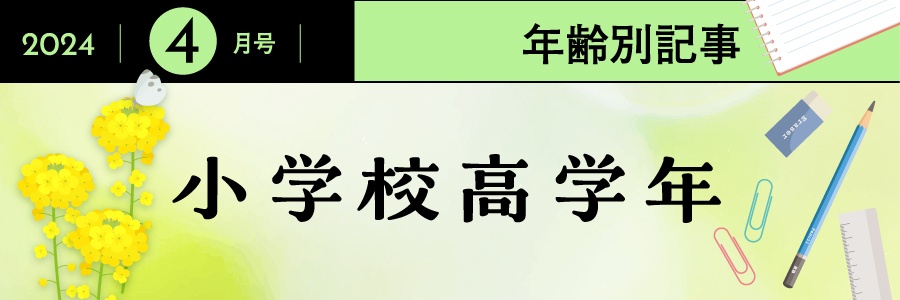ダメ嫁の汚名を引き受ける覚悟で、義父と取っ組み合い寸前の日々
「よき母であるとか、よき妻である以前に、『何としても事業を成功させなければ』。その一心で、とにかく夢中で仕事をしました。私は家事を一切やらないダメなママの汚名を引き受ける覚悟で家事の放棄をしたんです。いい嫁としてきれいごとを言っている場合じゃなかった。幸いなことに、継母が子どもたちの塾の送り迎えから食事の支度まで、まるで継母自身の第二の人生の生きがいとばかりに自分の役割として育児や家事に全面的に協力してくれました」
「私たちは継母のことを“しょうこばば”と呼んでいるのですが、しょうこばばのサポートなくしては今の私はありません」と阿久津さんは言います。
「家事には人それぞれやり方がありますから、継母に任せる以上、私は一切口出ししない、と決めたんです」
しかし、そんな阿久津さんの態度を義父は面白く思わなかったようだと振り返ります。
「『嫁とはこうあるべき』という昔ながらの慣習をよしとする典型的な旧時代の人でしたからね。『毎晩、姑のために嫁が寝具を整えるというのは美しい習慣だったな』などと言われたこともありました。でも下手に期待をさせてはいけませんから、『私がそんなことをするわけがないじゃないですか!』とすぐさま反抗しましたよ。可愛げのない、ダメな嫁だと理解してもらい、義父と境界線を引くことが必要だったんです。『掃除も洗濯もしない嫁なんて』と嫌みを言われたときは『じゃあ、お義父さんが私の代わりに仕事をしてきてくれますか?』と言い返しました」
義父はそれまで何十人もの部下を抱え、ずっと人の上に立って事業をしてきた人。阿久津さんのように逆らう人はこれまでいなかったはずです。理論で対抗しても駄目だと思った阿久津さんは、感情に訴える作戦をあえて選びました。
「動物が命を張ってマウンティングしあうみたいに、上から押さえつけるには感情を爆発させるしかなかった(笑)。激高した義父が『何を~!』と私の胸ぐらをつかみ、取っ組み合いの喧嘩寸前の言い合いをすることもあったほど。でも私も負けていませんでしたよ。『お義父さんが謝らなければ、私は家に帰りません!』と家出をしたこともあります。口にはしませんでしたが、義父には事業を失敗した借財があり、ダメ嫁でも私が働くことがいいことだと義父自身、心の中では思っていたようです。何よりも救いだったのは2人が衝突するたびに、しょうこばばが私のことを庇い、いつも味方してくれたことです。本当にありがたかったですね。長谷川さんは一人っ子の長男です。実母だったらこうはいかなかったはず(笑)」
「取引先に行く交通費にも事欠くようなどん底の生活で、なりふりかまっていられなかったこともありますが、『私一人ではできません。助けてください』と言葉にすることで開かれる扉があったと今では思えます。前の結婚で失敗したときの私は世の中が望むよい嫁を演じようと無理して何でも一人で抱えていました。でも人によく思われたところで、誰も助けてくれないし、何も解決しないですからね」
当時の景気のおかげもあり、ブライダル事業はたちまち軌道に乗り、経営は安定していきます。さらに銀行が合併するタイミングで不良債権処理で20億円の借金問題も解決しました。社員も増え、結婚する人口も多く、会社は右肩上がりに成長していきます。ところが、このころから夫婦としての二人の間には擦れ違いが生まれはじめ、喧嘩が絶えない毎日。
やがて二人は……。
* 次回に続きます。
(ライター/砂塚美穂、撮影/西山和希)