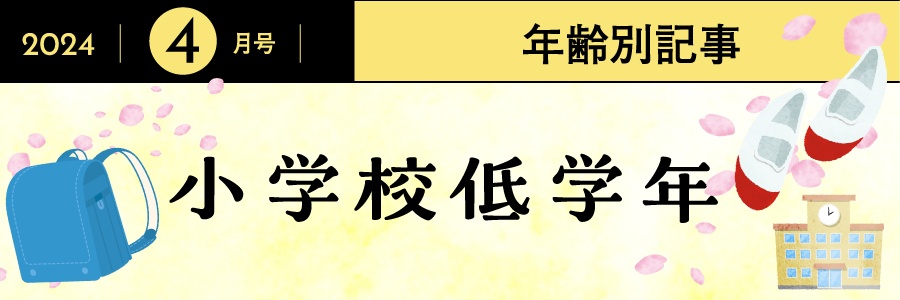床で寝てしまってもベッドに運んでもらえるお坊ちゃまにはなってほしくない
わたしは早生まれで、かつ発育の遅い子どもだった。
大学に入ってから身長が5センチほど伸びたのだから、本当に遅かった。そんな高校1年生だから、周囲の仲間が異様にたくましく見えた、というところがあったのかもしれない。
というか、ヤカンのラッパ飲みにたくましさを感じてしまう感受性のほうが、どうかしているという見方だってできる。飲めなくたって、いったい何が問題だというのか──と突っ込まれれば、なるほどそうだとうなずくしかない。
だが、理屈はどうであれ、あの時植えつけられてしまった考え方や劣等感は、50歳になった今も色濃くわたしの中に残っている。そして、できることであれば、自分の好きなタイプのオトコになってもらいたいな、との思いを息子に対して漠然と抱き続けている。
母親が子どもに手をかけるのは分かる。発育のためによくないものは口にさせたくないというのも分かる。
だが、そうした教えを忠実に守っていても、というより、守りすぎていると肩身の狭い思いをすることもあるのが、わたしの生きてきた世界だった。駄菓子の中には健康上あまりよろしいとはいえない添加物が含まれているかもしれない。けれど、そんなことは委細かまわずバリバリと咀嚼するキャラに、わたしは惹かれてしまうのである。
虎が床で寝ている。ヨメはかわいそうだと怒る。なんでベッドに連れていってやらないんだと怒る。
ごもっとも。
でも、床で寝てしまっても気がつけばベッドまで運んでもらえるというのが当たり前のお坊っちゃまに、虎にはなってもらいたくない──とわたしは独りごちる。