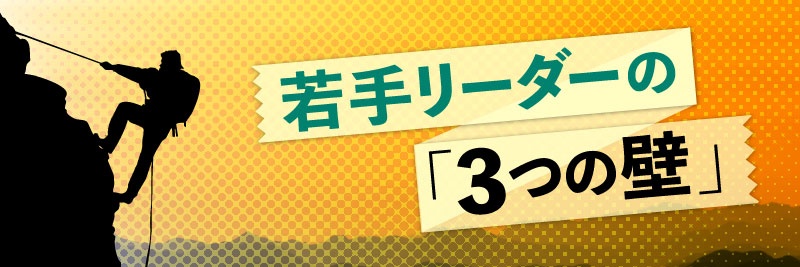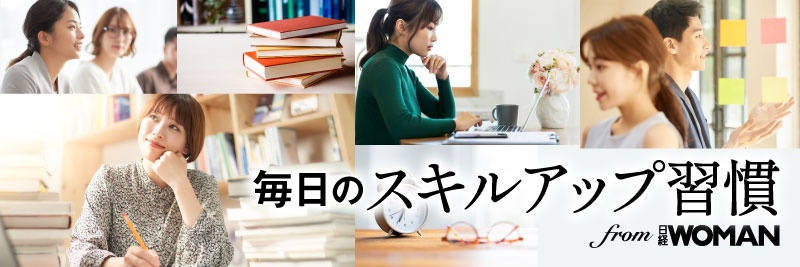「リーダーになるか否か」の入り口で迷う日本のワーキングウーマン

ギンカ・トーゲル教授
羽生 トーゲルさんには今まで何度かインタビューをさせていただいています。今回は、働く女性とリーダーシップについてお話をお聞かせください。
トーゲルさん(以下、敬称略) リーダーシップの役割の定義は2つあります。
1つは方向性を示すこと、もう1つはモチベートすることです。
ただ、どのようなリーダーになるかという以前に、日本のビジネスパーソンの反応で非常に驚いたことがあります。
2日ほど前、IMDの日本のアルムナイ(修了者)クラブのメンバーである、様々な企業の男女数十人と会って話す機会がありました。その会場で男女混合の3人ずつのグループに分かれてもらい、3人に1枚ずつ紙を渡して私に聞きたいことを書いてもらいました。1グループ1つ、合計で約20の質問が集まったわけですが、「女性はなぜリーダーにならなければならないのでしょう?」「どうやったら、リーダーになるように女性を励ますことができるのでしょう?」といった、ある意味、女性とリーダーシップというテーマの“入り口”のところの質問が多かったのです。
このことから、日本の企業でリーダーになるということに対して、「ワーク・ライフ・バランスを取ることがとても困難になるため、リーダーになるのは気が進まない」と思っている女性が多い、あるいはそもそも「女性がリーダーになるというのはどういうことか」ということについての理解が進んでいないことが考えられます。
「リーダーになりたい。そのためにはどうしたらいいのか」という議論の前に、日本では「そもそも女性自身がリーダーになりたいか、それともなりたくないか」という議論のほうが非常に強いようです。
―― そうしたリーダーシップの方法論以前の議論は日本特有のものなのでしょうか?
トーゲル 統計的に分析したわけではありませんが、インドでも中国でも、このような質問を受けることはありませんでしたから、こうした反応は日本特有だといえるかもしれません。これは日本社会における女性のイメージと関係している現象のように思えます。女性は優しく献身的といったイメージ。従属的という言葉は使いたくありませんが、それが女性らしさとして期待され、それがすなわちフェミニンなことであるという期待があるのかもしれません。女性が管理職として仕事をするということは、優しく献身的というイメージとの間でハレーションを起こしてしまいます。
―― その点、アメリカの女性はどうでしょうか?
トーゲル アメリカでは女性は明らかに「リーダーになりたい」と思っていますし、男性は、リーダーである女性が自分のパートナーであることを誇りに思う傾向があります。
―― 日本ではそうした男性はまだ少ないですね。