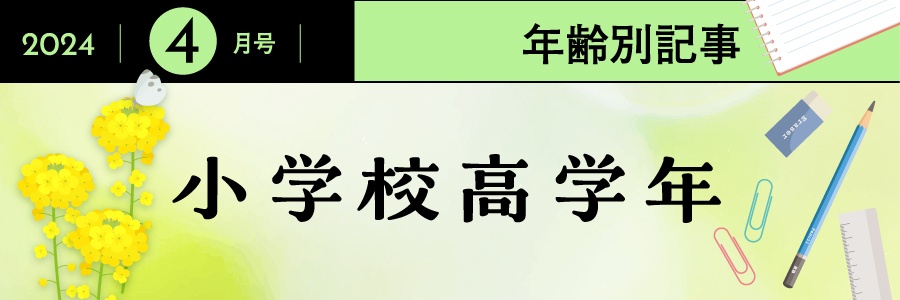思うに──いや、思わなくてもこれは真実だろうけれど、夫であれ妻であれ、思い切り仕事をしようと思えば、家庭に「専業主婦的役割」を引き受けてくれる人が必要なのである。急な発熱や病気がある以上、保育園やシッターの対応だけでは限界があり、どうしたっても無理なのだ。そして、これも言うまでもないことだけれど、たとえ共働きでも、こうした子どもの対応に駆り出されるのはほとんどが母親。「専業主婦的役割」をしてくれる祖母や祖父がいない場合、つねに仕事を中断することになり、板挟みになる心身の苦労はいかばかりだろう。「いっそ、仕事やめたほうがラク」と思うのは、弱音でもなんでもない、必然かつ道理的な流れだと思う。
6分の1くらいしか仕事できず、いつも悔しい
保育園やシッターがあっても、育児をして、出産以前のようにばりばりと仕事もやるなんて、本当は無理なのだ。だから自分の仕事のやり方を変えるか、子育てをしている相手と話し合って環境を変えてゆくしかないのだけれど、しかし内なる自分の声と世間は「何があっても、女性は仕事を続けるべき。自由になるお金は確保しておけ」と鼓舞してくれる。もちろんこれだって真実だとは思う。でも、家に「専業主婦」がいなければ、そんなこと、夫も妻も無理なのだ。「とはいえ、ミエコさんすごい仕事してるじゃないですか」と言われることもあるけれど、自分としては6分の1くらいの仕事量しかこなせていない、というのが、嘘偽りのない実感なのだ。誰に言ってもしょうがないし意味ないけれど、いつだって悔しいしすごく焦っている。3年以上がたってさすがに慣れてきた部分もあるけれど、今でも夜中なぜかぱっと目が覚めて、「仕事がしたい……!」と、がばっと飛び起きてしまうこともある。
そんなだから、たとえば男性の研究者や学者の功績などがニュースで報道されるときに、内助の功、みたいなかたちで専業主婦の奥様が紹介されたりなんかすると、なんなーく複雑な気持ちになってしまうこともある。もちろん、そのお仕事が評価されることじたいは本当に素晴らしいことであるのは大前提で、しかし、どこかで、「……育児、家事は妻に任せて自分は仕事だけしていればよかったんだから、それはよかったですよねえ」みたいな、そんなもやっとした気持ちにもなるのである。
そしてたまーに会う「ほんと、ぼく仕事忙しすぎて大変だけど、なんかできちゃう男なんですよね、今月海外出張3回ですよー」みたいな「仕事できる自慢ノリ」の男性実業家とかにそういうことをアピールされると、「……家のことぜんぶ人にやってもらってるんだから、仕事ぐらい、できて当たり前なんだよ」と冷たい目でみてしまう。あるいは、女性作家やアーティストが「女性は子どもを生んでも、ぜったい仕事を続けるべき。がんがん稼ぐべき(自分みたいに)」と自信満々に話すとき、しかしたいていは家に「おばあちゃん戦力」に類するものがあって、子どもの面倒を何から何まで見てもらっている場合が多い。多くの女性に、「おばあちゃん戦力がない」ことを想像できない鈍感さにもイラッとするし、内実は「専業主婦に家のことまかせて仕事だけしている夫」とさほど変わらないのに、そのことに気がついていないのもどうなんだろうと思う。
そして何よりもイラッとするのは自分自身にたいしてであって、本当に仕事がしたくてたまらないとき、「ああ、わたしにも専業主婦がいたなら……!」とつい、そんなような利己的かつマッチョなことをつい夢想してしまうのだ。恐ろしいことである。