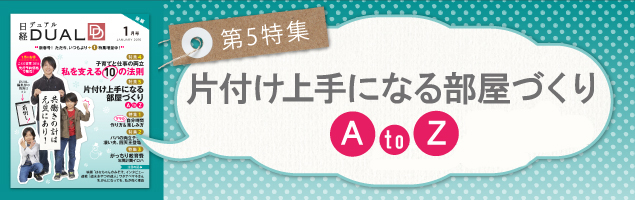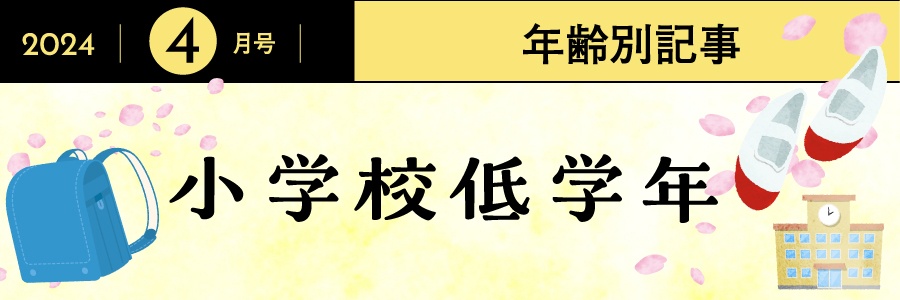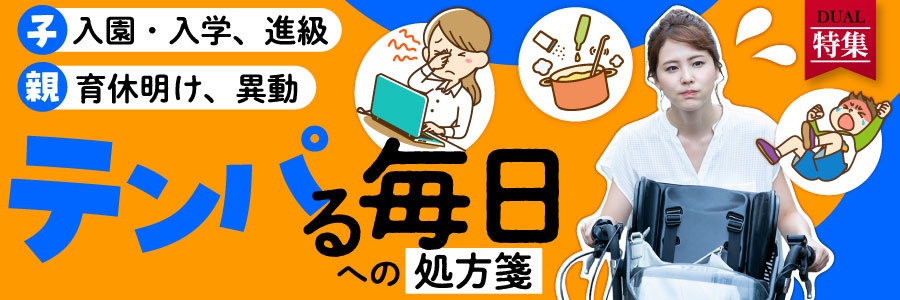第1回「『片づけなさい!』は“無茶ぶり”だった!」でも書いたように、子どもがスムーズに片づけを習得するには、発達の段階に合わせた言葉がけが重要になる。
ここからは「乳幼児期」と「小学校入学以降」に時期を分けて、子どもの片づけ力を高めるポイントを紹介しよう。
自分からすすんで片づけができる子どもに育てば、「片づけなさい!」とハッパをかける必要もなくなる。親がラクになるのはもちろん、「将来、身の周りを自己管理できる自立した社会人へと成長を促すために、小さいうちからのはたらきかけが重要」(一般社団法人日本収納検定協会代表の小島弘章さん)なのだ。
まずは、乳幼児期にやるべき働きかけから。とはいえ、0~2歳の時期は、目につくものすべてに興味がわいて、「出したモノを片づける」という行動を覚えることはまだまだハードルが高い。
「片づけ」には、「モノの種類を分類」→「あるべき場所にしまう」という2段階の行動を要するが、「モノの分類ができるのは、食事や着替えなどができるようになってくる3歳以降」(実践女子大学生活科学学部教授の松田純子さん)。2歳くらいまでは遊びを優先して、片づけも遊びの一環として「箱にモノを投げ入れて、全部入ったら褒める」など子どもが楽しめる演出を心がけよう。
色や形に興味を持ちはじめたら、「青いおもちゃは青い箱、赤いおもちゃは赤い箱に入れてみよう!」「丸い形のモノと、四角い形のモノで分けられるかな?」など、分類遊びにトライ。こういった分類遊びは「思考や認知の能力を高める、非常に高度なトレーニングになる」(松田さん)。
大事なのは、子どもができた時にたくさん褒めること。
「モノをしまうとお母さん、お父さんが笑顔で喜ぶ。親がポジティブな反応を見せ続けることで、“片づけは楽しい”“好き”“得意だ”という積極的な姿勢が育っていく。このベースができると、その後の収育(=片づけ教育)がとってもラクになります」と小島さん。