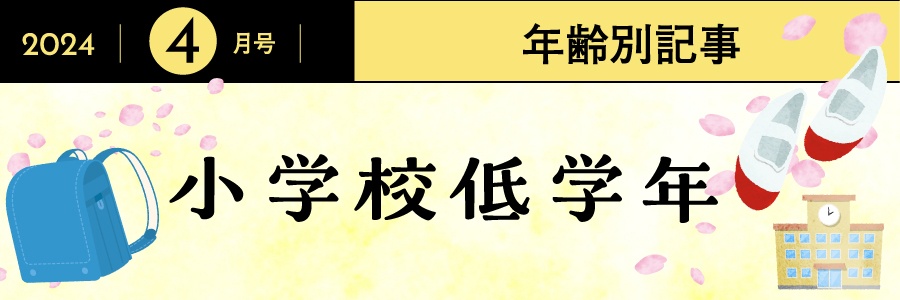「我が子の発達をあきらめる母親などこの世にいない」
その当時、施設の言語聴覚士であるM先生の指導のもとに、職員全員が加寿代ちゃんに指文字を教えて、彼女とコミュニケーションをとろうと試みていた。言語聴覚士とは、言語発達に遅れがある子どもや、脳梗塞などで言語障害になった患者の言葉の訓練をする専門職である。
まず、指文字で「好き」と「嫌い」を教えることになった。自分の手の甲あるいは相手の手の甲を手のひらでぽんぽんと叩くのが「好き」、人差し指でつんつんとつつくのが「嫌い」。
3年間試みを続けたが、何の成果も上げなかった。年に1回ある検討会で、3年間の努力は無駄だったのではないか、加寿代ちゃんに指文字を理解させることなどしょせん無理なことなのではないか、という意見が看護師らのグループから出た。
能力のない者に能力以上のものを教えようとする行為は無駄だから、一刻も早く見切りをつけるべきだ、と考えているようだった。看護師側の意見は強硬だった。
加寿代ちゃんに指文字を教える試みは、M先生だけの努力では成功しない。加寿代ちゃんに関わるすべての職員が、一貫した取り組みをすることで初めて成し遂げられるものだ。従って、看護師らの協力が得られなければ、この試みはとうてい成功しない。
30人以上いる看護師対たった1人のM先生。会議のゆくえを見守っていた私は、M先生が看護師らの意見に押し切られて、この指導プログラムを強制終了させられることになるだろうと思った。
M先生は静かに言った。
「障害児療育が失敗する原因のほとんどは、成果が出る前にあきらめてしまうからだと思います。あきらめずに愚直に成功するまで続けること。3年やってダメなら、4年やる。4年やってダメなら5年やる。それが大切だと私は思います」
加寿代ちゃんの指導を巡って職種間の対立構図が鮮明になり、会議室の空気に緊張感がみなぎった。しばらくの沈黙の後に、医師である私に、意見が求められた。
私は、私の意見がこの会議の結論を決定づけてしまう可能性があることを意識しながら、慎重に言葉を選びながら次のような意味のことを話した。
「生まれたときから家族の愛情を受けることなく育った加寿代ちゃんに、M先生は加寿代ちゃんの入所以来ずっと寄り添ってきた。いわば、M先生は加寿代ちゃんの母親だ。我が子の発達をあきらめる母親などこの世にいない。そして、施設の子どもたちがここにいる間は、すべての職員は父親であり、母親でなければならないと思う」