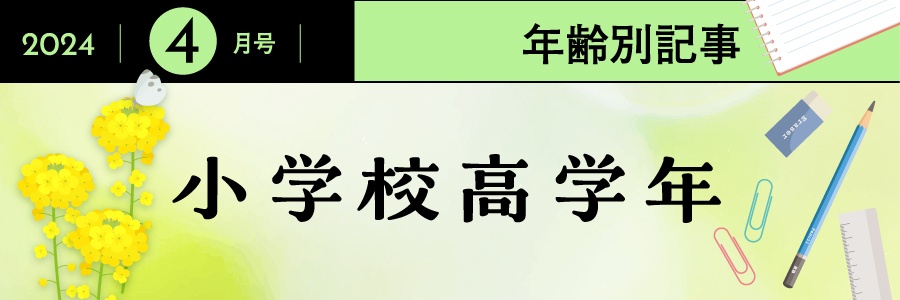本が大好き。でも劣等感の塊でした
―― 小手鞠さんが作家をめざすことになる原体験について教えてください。

左:小手鞠さん(中央)を囲む父と母 右:3~4歳。山のように積み上げられた絵本に手を載せて。「本が大好きだった」
小さいころから本が大好きで、両親も本は無尽蔵に買い与えてくれました。私がまだ3歳か4歳ごろでしょうか。家の中に積み上げられた本に手を置いて、満面の笑みを浮かべている写真が残っているんですよ。
本は大好きだったけれど、小学生のころは作家になるなんて、夢としても自覚していませんでした。
そして、中学校に上がるころには私は劣等感の塊で、暗く沈んだ毎日を送っていました。劣等感の原因は、分厚いメガネです。本の読み過ぎで目が悪くなってしまって、当時はコンタクトレンズもなかったので、厚いレンズのメガネをかけるしかなかったのです。多感な時期の女の子にとって、目が小さく見えるメガネをかけるって本当に絶望的な気持ちになるものでしょう? 学校でも「私なんて…」と小さくなって過ごしていました。
人生を変えた1冊の青い詩集との出合い
そんな私にとって運命の出合いとなったのが、1冊の青い詩集でした。詩人として活躍していたやなせたかし先生が40代後半のころに出版した『詩集 愛する歌 第2集』。「中1コース」という月刊雑誌のアンケートに回答したハガキが抽選に当たって、プレゼントとして送られてきたのです。ページをめくって、そこに広がる、美しい愛の世界に私は夢中になりました。夢中になるうちに「こんな私でも、何か書けるかもしれない」と思い、書いてみるようになりました。
そして、見よう見まねで書いてみた「菊」「乳液と弟」「八月二十日の父」という3篇の詩を、所属していた文芸クラブの顧問の先生がとても褒めてくださったんです。赤木久児(ひさこ)先生という女性の先生で、厳しくも情熱的に指導をしてくださる方でした。
両親に厳しく育てられた私にとっては、「自分が書いたものを褒めてもらう」という経験がとても大きな意味を持っていたのだと思います。
後に私は、やなせ先生が編集長を務めた雑誌『詩とメルヘン』に作品を投稿するようになり、賞をいただき、詩の創作から文芸の道を歩んでいくことになります。書く喜びと、人に褒められてうれしいと感じる気持ち。この二つの幸福との出合いが、私のその後の人生を決定的なものにしたと思います。
(ライター/宮本恵理子、写真/小野さやか)