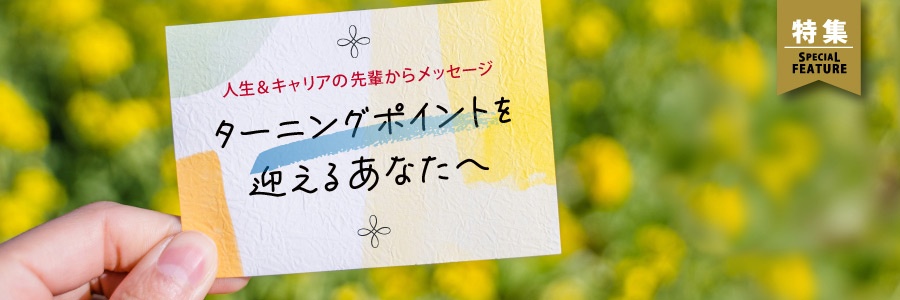このケースのように、他者比較ではなく自己理想(フルマラソンを完走したい)と現実(今は完走するほどの実力がない)とのギャップを認識することも、アドラー心理学では「劣等感」と捉えます。たまに「私って劣等感の固まりなの」と、劣等感を持っていること自体に劣等感を抱いている方に出会いますが(笑)、劣等感そのものは病気でもなんでもなく、誰もが持っているものです。アドラーは「劣等感はむしろ健康で正常な努力と成長への刺激である」と言っています。
学歴や家柄、人脈などを自慢する人の心理とは
ところで、皆さんの周りには、自分の親やパートナーの学歴、家柄や人脈などを自慢する人はいませんか? これは「優越コンプレックス」といって、上述した劣等コンプレックスの一種と言えます。このような人は、何らかの負い目(主観的な劣等感)を感じています。その劣等感を建設的に克服することから逃げて、これなら努力せずとも勝てると思えることを、ことさらにひけらかすことによってその負い目を埋め合わせようとしているのです。
劣等感についてお話ししていると、よく「そうは言っても、私は○○というハンディキャップがあるから、どうしようもないんです。建設的な対応なんて考えられません」という反応に出会います。アドラー心理学では、身体の器官などに客観的な事実としてのハンディキャップがある場合は「劣等性」という言葉を使い、これまで説明してきた「(主観的な)劣等感」と区別します。
このような、一見、建設的な対応ができそうにない場合でも、実際には、劣等性をバネにして大きな成果を上げている人もたくさんいます。例えば、棟方志功は極端に視力が悪かったことをバネにして、目を使う仕事である版画家として成功しました。あるいは、盲目の音楽家スティーヴィー・ワンダーは、不自由な目の代わりに耳を武器にして世界的な成功を成し遂げたのです。