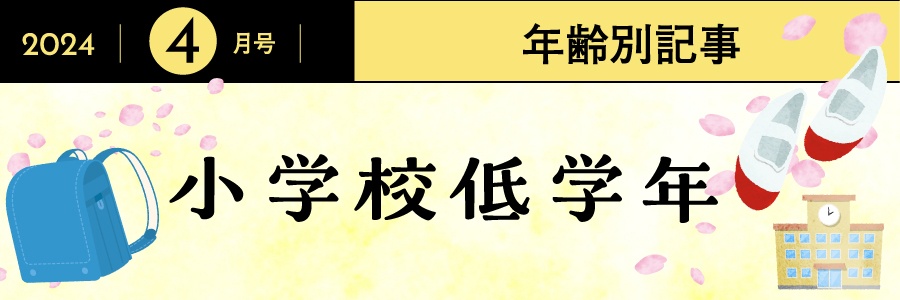母は椅子から落っこちそうになるくらい驚いた

パリと東京を拠点に活躍する照明デザイナーの石井リーサ明理さん
日経DUAL編集部 「明理」というお名前にはお母さんの深い思いが込められていますよね。
石井リーサ明理さん(以下、敬称略) よく「アーティストネームですか?」と聞かれるのですけれど、本名なんですよ。私が生まれたとき、母は他にいい名前が思い浮かばなかったのですかね?(笑)
―― やはり小さいときから、お母さんと同じ仕事をしたいと考えていたのですか?
石井 いいえ、大学院に行くまで全然思っていませんでした。大学院に入って、デザインの勉強をしにパリに留学したときに、光の街と言われているパリで、最先端の照明デザインをやっている方に色々とご指導いただく機会があったのです。そこで、光に強く興味を持ちました。光は、建築にも写真にも、映画にも絵画にも共通する大事なテーマです。もともとクリエーションの仕事を志していましたので、光を使ったクリエーター、すなわち照明デザイナーになりたいと思うに至ったのです。
そこで日本に帰国してから「照明デザインをやりたいと思う」という話を母にしたところ、母は椅子から落っこちそうになるくらい驚いていましたね。
―― つまり、お母さんは明理さんが同じ照明デザイナーになると期待していなかったと?
石井 そうですね、そういう気配がなかったからだと思います。東京藝大の美術系の学部で建築とか都市計画を真剣にやっていましたし、大学院まで行ったので、父(法制史学者の石井紫郎さん)と同じ研究職を目指すことも考えてはいましたから。ですから、母も驚いたのでしょう。私が23歳のときです。
「おかえりなさい」と迎えてくれる人がいた
―― 明理さんの生まれる3年前の1968年、石井幹子デザイン事務所を設立したお母さんは、70年の大阪万博や75年の沖縄海洋博の照明デザインを手がけるなど、日本国内はもちろん世界を舞台に活躍していました。幼心にどんなお母さんと受け止めていましたか?
石井 ごく普通に、「お母さんはお仕事をしていて、夜帰ってくる人」という受け止め方でした。照明はどうしても、日が落ちて暗くなってからの調整や実験が必要なので、帰宅が夜遅くなるときも多かったですね。逆に父は大学で教える研究者でしたので、帰宅は割と早く、晩ごはんは父と二人ということが多かったですね。
―― 学校であった出来事などを話すのも、夕食のときにお父さんに?
石井 日常的な学校での出来事は、祖母に話していました。祖母は一緒に住んでいなかったのですが、学校から帰ってくる時間帯には家に来てくれていて、「おかえりなさい」と迎えてくれました。そして、おやつを食べさせてくれて、習い事のことを見てくれたりもしました。身の回りのことをしてくださる方が長く一緒に住んでいて、その方ともよく話をしていました。