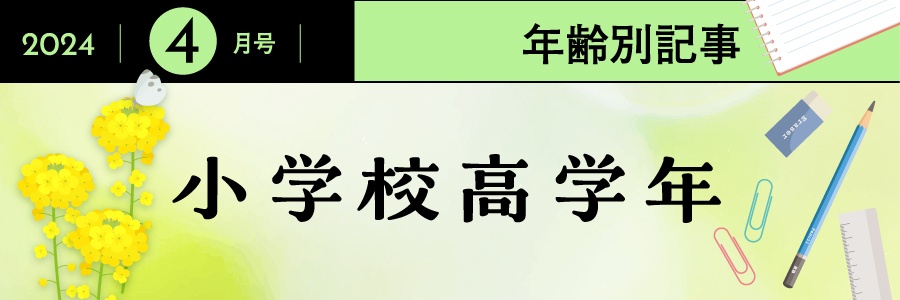出産したら作風が変わったと言われたくない
―― 「子どもがいることはあまり公にしたくなかった」とは、どうしてだったのですか?
確実に言えるのは、出産は女性作家にとってものすごい「変化」と受け取られるだろうなということ。何を書いても「母になったからですね」と言われてしまうことに抵抗がありましたし、自分が読者だったとき、10代の気持ちが描かれた小説に共感してきました。それが親になったことで「書けなくなった」と受け止められたくなかった。子ども側の見方ではなく、一気に大人の側の作家だと思われてしまうのではないか。そんな危惧がありました。
母親になった=「変化」と受け取られることがなぜ嫌なのか。いまだに理由を明確に言葉にできていない部分も多いと思っています。思いとして強くあるのは、何も自分が選んだ、結婚・出産というその生き方だけを正解だと思って生きているわけではないということです。
―― そこだけが正解とは思っていない、ですか。
私は今、たまたま結婚して子どもがいますが、だからといってその生き方を人に勧めたいかというと必ずしもそうではありませんし、他の生き方をしている人達の多様性を認めない考え方はしたくない。自分の現状を「正しい」と思っているわけではないんです。
けれど、女性にとってはやはり、結婚と出産は大きな岐路ですから、自分が進んだ道とは違う道を選択した人のことは気になるし、意識する。ライバル視することもあるかもしれないし、反対に向こうが自分をどう思っているのかも気になりますよね。小説を書くに当たっても、どちらかの生き方を「正解」のように押し付けたりするようなことはしたくありません。「いろんな生き方があっていい。たまたま私はこうですけど」という部分をすごく大事にしたい。
この私の譲れない部分が、出産したと公表することへの抵抗を大きくしていたのかもしれません。渦中のときは全然言葉にできなかったけれど、ようやく今、整理できるようになってきました。
―― 作家という職業に限らず、女性の生き方を語る場合、子持ちvs子なしという対立軸で語られがちですよね。
結婚もそうですね。私の場合は結婚したときも同じように、「これで辻村深月の小説はつまらなくなると言われるに違いない」と思っていました。
―― 読者感覚として分からなくないです。女の日の当たる生き方は「結婚・出産・子育て」だといまだに刷り込まれている部分は多くて。女性作家はそのマイノリティーでいてほしい、不遇だからこそ面白い小説が書けるはずだと、勝手なイメージですが。
結婚したら、離婚もセットでこそ作家だとか(笑)。結婚して書くものがつまらなくなると恐れていたなんて、結婚=平穏だと信じていた当時の価値観は未熟だったと情けない部分もあります(笑)。