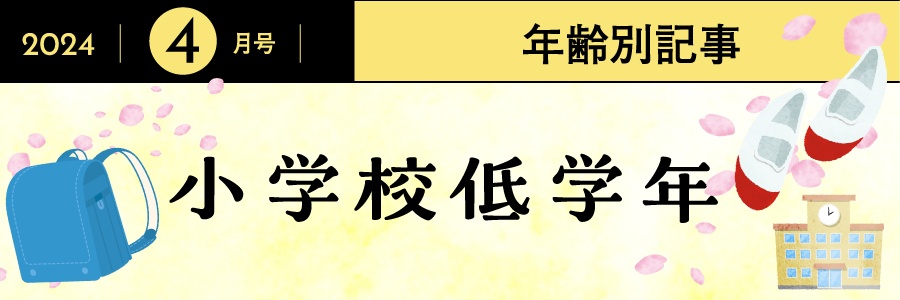母親になっても、自分の譲れない部分はある
―― 特別養子縁組によって男児を授かった40代の佐都子。中3で出産するも育てられず孤立していく10代のひかり。2人の主人公を、辻村さんはどうご自身に引き寄せていったのでしょう?
実感としてあるのは、出産したからといって、急に母親になれたり、母性が湧いてきたり、尊い何者かになれたりするわけではないということ。私の場合は、出産したら気持ちが優しくなってホラー映画が見られなくなったりするかな、と思ったら、変わらず大好きだし、殺人が起こるミステリーも相変わらず読みます。子どもが寝静まった後の楽しみでもあるし、自分の欲求だって、当然変わらずあります。
子どもは大事な存在だしかわいい。だけど、すべてを子ども優先にできるかというと、自分の中で譲れないものだってある。親になったからって、まだまだ生身のままだと気づく瞬間って、どのお母さんにもあると思います。
ただ、実際は出産してもそんな感じなのにもかかわらず、周囲からの、“産めば母になれる”と信じられている目線に苦しめられ、束縛を感じている女性もいると思うんです。小説の中で、若くして出産を経験したひかりは、出産はしたけれど世間一般で言われている母性像からはみ出し、中ぶらりんのまま追いつめられていく。佐都子は、産むことはかなわなかったけれど育児をするうちに、母親と呼べる存在になっていた。出産をしている、していないということを超えた母性について、書くうちにだんだん私の中で見えてくるものがありました。
―― この中には、辻村さんご自身が子育てで得たものが象徴として入っているわけですね。
そうですね。今、自分が子どもと一緒に暮らしていることがすごい巡り合わせで、偶然の上に成り立っているものなんだということも思い知りました。
ただ、今となっては、こんなふうに子どもがいることを前提に話をしていますけれど、出産して2年ぐらいは、自分に子どもがいることをあまり公にしたくありませんでした。
※後編「自分の人生選択を『正解』と思わない」に続きます
(取材・文/平山ゆりの 写真/鈴木芳果)