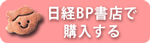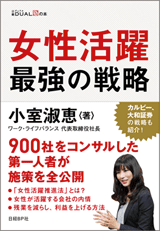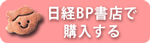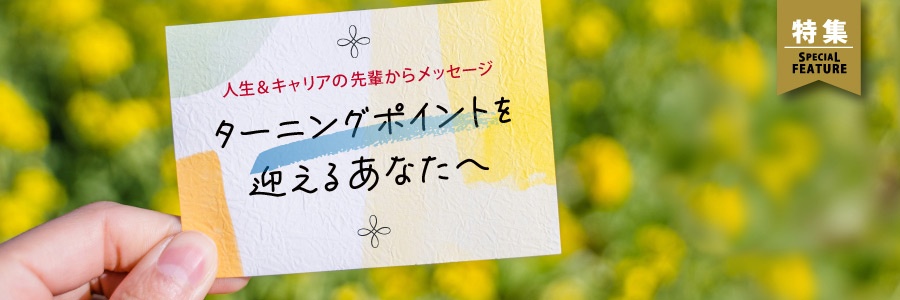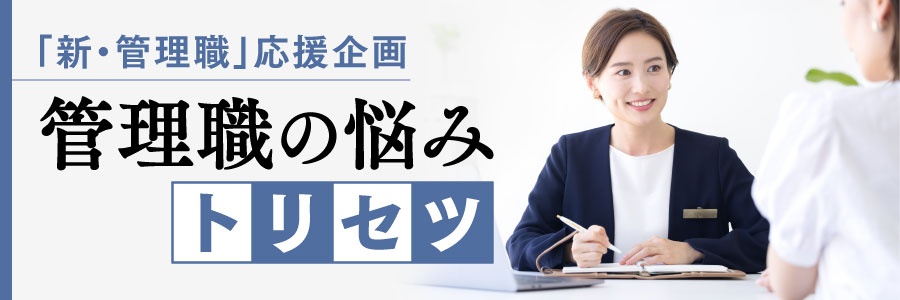建設コンサルで改革に挑戦 残業5%減、利益倍増
パシフィックコンサルタンツ(上)/業界全体が抱える優秀な若手の流出や女性活躍を阻害する「長時間労働の弊害」に挑む
長時間労働を減らすにはどのような施策が必要でしょうか。先日、ワーク・ライフバランス社主催で経営者限定の働き方の改革についての勉強会が行われました。ゲストスピーカーは総合建設コンサルタントのパシフィックコンサルタンツ株式会社の長谷川伸一会長とワークライフバランス推進担当の広報室の油谷百百子さん。残業を5%削減し、利益を2~3倍に増やした同社の事例について、ワーク・ライフバランスの小室淑恵社長と語り合います。上下の2回に分けてお送りします。
【パシフィックコンサルタンツ】
戦後日本の復興のために1951年に創業した建設コンサルティング企業。社会資本整備を主体とする公共事業が約85%を占め、主な顧客は国や地方自治体。社員の80%が技術者で、土木、都市計画、建築のプロフェッショナル。業務内容は社会インフラ全般の企画、調査、設計、施工管理、維持管理で、最近は防災・減災対策や、災害からの復興、地域活性化や老朽化した公共施設の維持管理、エネルギーなどに一貫性を持って取り組んでいる。
働き方の改革に着手した理由は、経営を改善するためだった
長谷川会長(以下、長谷川) 建設コンサルタント業界は欧米では100年から200年くらいの歴史があり、価格よりも技術の成果によって金額を決めることが多いのですが、日本では戦後誕生したため50年から60年ほどとまだ歴史が浅く、公共予算との関係から「安ければいい」という風潮が根強く残っています。
私が若いときには確かにこの業界は“男の仕事”と言われ、自己犠牲の上に成り立っていました。社会に貢献する誇りを持ちつつ、国土を作っているのだから残業は当たり前じゃないかという意識で、会社に寝泊まりしながら頑張っていた世代が今の経営者となり、長時間労働の改善になかなか意識がいかない。私はなんとかその呪縛から抜け出したいと思っていました。
小室さん(以下、小室) 2012年に働き方の改革に挑む前は、仕事の山が毎年3月に集中していましたよね。公共事業の予算の都合上、3月に納期が集中するという背景がありました。
ところが3年間、働き方の改革に取り組まれたことによって、利益や受注高が良い形で変化したんですよね? このように変わるにはどのような意識で取り組んだのでしょうか?
長谷川 実は自分以外の役員達は長時間労働をやめることによる経営への悪影響を心配していました。「残業せずにどうやって経営を成り立たせるのか」と。お客さんの要望にすぐに応えられなければ、お客さんが離れていってしまうのではという恐怖感があったのです。
ところが長時間労働を続けていると、サービス残業により労災認定をされるケースなど、企業そのものが指名停止処分を受ける恐れもあります。また、当時は公共投資に対するバッシングがあり、売り上げも落ちている時期でした。利益も下がりぎみで長時間労働のウエイトが高くなり、“損益分岐点”が上がっていました。それでは経営が成り立ちません。ならば「長時間労働をなくせば経営が改善するのではないか」ということで、多くの役員が納得するに至りました。

左から、小室淑恵さん、パシフィックコンサルタンツの長谷川伸一会長、ワークライフバランス推進担当の油谷百百子さん
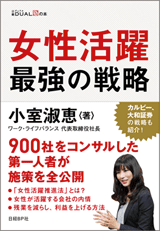
「長時間労働を削減し、勝ち抜ける企業に」 DUALの本
『女性活躍 最強の戦略』 予約開始!
著者/小室淑恵
価格/1620円(税込み)
【第1章】女性活躍・推進編
女性の活躍が必要な「そもそもの理由」/「女性活躍推進法」とは?/大和証券グループ「社員が安心して活躍できる職場づくり」/カルビー「時短女性が役員を務める会社の内情」
【第2章】長時間労働・撲滅編
長時間労働は全員でやめないと、誰かにツケが回る/成果につながる長時間労働の削減、3つのコツ/セントワークス「残業時間に『恥ずかしいマント』着用で利益急増!?」
《スペシャル対談》小室淑恵×日経DUAL編集長・羽生祥子