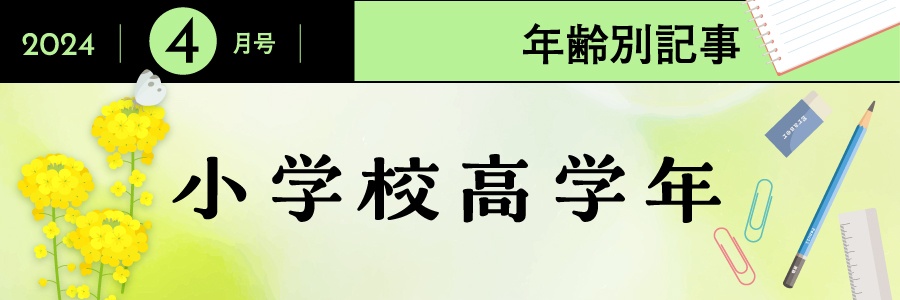1年間の「休暇」中にイースト・ハンプトンにて、一家で迎えたクリスマス
イースト・ハンプトンの「休暇」は母からの最高のプレゼント
日経DUAL編集部 桐島さんが小学2年生のころ、一家はアメリカに1年間移住することになります。
桐島ローランドさん(以下、敬称略) 母が30代最後の1年は「休暇」にしようと決心して、ニューヨーク郊外のイースト・ハンプトンに家を借りて一家で暮らすことになりました。この経験について、僕は本当に母に感謝してるんです。僕の人生にとってこれ以上は考えられないほど貴重な経験で、母からの最高のプレゼントだったと思うくらい。
―― それほどまで思えるなんて、どういうところがよかったのですか?
桐島 何より、アメリカの自由なところですね。教室に行ったら机が並んでいないどころか、「どこでもいいから好きに座りなさい」って言われる。それに、僕は日本の学校にいたころ、ハーフだという理由で結構いじめられたんですが、アメリカでは大歓迎。みんながすごくフレンドリーに接してくれて、学校が本当に面白くて、英語もすぐに話せるようになりました。
母は英語に時間とエネルギーをかけ過ぎる日本の教育に疑問を持っていて、英語を自然な生活の一部として早くから子どもに植え付けたい、とも思っていたようです。
それから、アメリカでは小学2年生で九九ができると天才児扱い。毎日算数は満点で、皆に尊敬の目で見られて非常に気持ちがよかったんです。母は子どもの成績には興味が無かったので、「100点取ったよ!」と言っても「ああ、そう」という感じでしたけれど。