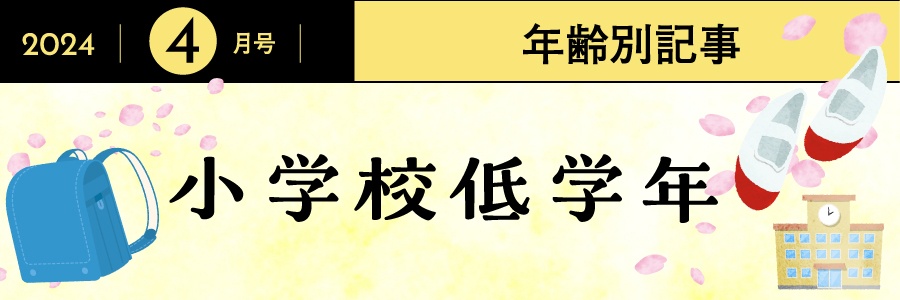アメリカで知った、忘れられない「おふくろの味」

『聡明な女は料理がうまい』の著者の料理は「おいしいですよ、ものすごく」とローランドさん。「それを毎日食べられたのもアメリカ暮らしの楽しみでした」
―― 『マザー・グースと三匹の子豚たち』には、「子供たちとバッチリ顔つき合わせ、私の知力と経験と偏見と哀歓とをぶちまけて、思いっきり彼らを鍛えてみよう」と、アメリカでの1年間子育てにきちんと向き合いたいというお母さんの思いがつづられています。アメリカに移住して、お母さんとゆっくり接することができたと実感しましたか?
桐島 そうですね。母は日本にいるときからは考えられないくらいほとんど家にいて、初めて長い時間を共に過ごしたと感じました。日本の雑誌などで連載を持っていたので、相変わらず家で仕事はしていましたが、日本にいるときよりもリラックスしていましたし。母、姉二人と家族の絆が深まったと思います。
イースト・ハンプトンは東海岸の人達にとっての避暑地で、のんびりとした本当にいい所。近くに海もあって、週末は皆で自転車に乗って出かけました。自然に恵まれ、どこに行っても遊ぶ所だらけで楽しかったですね。
あと、日本にいるとき、食事はたいてい祖母か家政婦さんが作ってくれていたんですが、アメリカでは母の手料理が毎日食べられたのもうれしかったですね。イースト・ハンプトンは港町なのでシーフードが豊富で、ムール貝を皆で拾って食べたりとかもしました。貝柱のバターソテーも、子ども心にものすごくおいしくて、今でも母に「作って」とリクエストすることがあります。
―― 楽しい1年もあっという間に過ぎ、お母さんが仕事のために日本に帰国しようとすると、子ども達は大反対。結局、学年末までの半年間、子ども達だけでアメリカに残ることになるのですよね。そのときのことを、お母さんは「彼らが母を必要としなくなったいま、私はさびしく、そしてうれしい」と表現されています。
桐島 母はベッチーという住み込みのベビーシッターを雇い、子ども達だけでアメリカに残してくれたんです。そのベッチーが料理上手の母とは真逆で、ああ、今でもよく覚えているけど、毎日ポークチョップとビーツの缶詰の日々で……。今でこそ日本でビーツは「おしゃれな野菜」扱いですが、僕にとってはもうトラウマ(笑)。色々大変な目には遭いましたが、それでも子ども達だけで、残りのアメリカ生活をたくましく楽しみました。
ガードレールを付けないのが、アメリカ流子育て
―― 「かわいい子には旅をさせよ」を地でいく子育てだったのですね。
桐島 アメリカ生活で僕が一番学んだのは、サバイバル能力だったと思います。もちろん家族という絆も大切だけれど、最終的には自分一人で生き残るたくましさが必要。それが、母が子ども達に伝えたかったことという気もしています。
「Take your own risk.(自分で自分のリスクを負いなさい)」。これは母がよく使っていた言葉。自分で自分のリスクを背負えるようにならないと、独立できず、いつまで経っても自由になれないということです。アメリカではグランドキャニオンから毎年何人も落ちて命を落としているけれど、日本と違ってガードレールは付けたりしません。「グランドキャニオン、これより先は危険」という看板が立っているだけ。うちの母の子育ては、まさにこのスタイルだったとも思いますね。