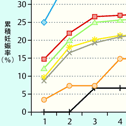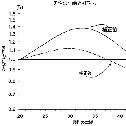2012年、日本で生まれた子どもの27人に1人が「体外受精児」
前回記事「不妊治療、いい病院の選び方と治療ステップ」では、妊活カップルが実際に病院に行く目安、病院での検査、そして治療のステップ(人工授精まで)を説明しました。今回は、その続きをお話ししていきたいと思います。
人工授精で妊娠に至らなかった場合の次の治療は、体外受精(英語では「In Vitro Fertilization」、略して IVF)です。
体外受精は、イギリスの医師、ロバート・G・エドワーズと、パトリック・ステップトーによって、1978年に世界で初めて成功し、その結果、ルイーズ・ブラウンさんが誕生しました(*1)。
当時、試験管ベビーと呼ばれていたこの方法は、徐々に広まり、世界で約400万人の子どもが体外受精によって誕生したと言われ、この功績によりエドワーズ医師は、2010年にノーベル生理学・医学賞を受賞しました(注:ステップトー医師は既に死去していたため、残念ながら授賞対象になりませんでした)。日本では、83年に最初の体外受精児が誕生し、以降、約30年の間に、累計約30万人の子どもが体外受精によって生まれています。2012年一年を見ると、日本で生まれた子どもの27人に1人(3万7953人)が、体外受精児として誕生しました。
体外受精は、採卵針を用いて卵巣から卵子を体外に取り出し(採卵)、培養皿の中で精子と合わせて受精させる方法です。その後、受精して分割した卵子(受精胚、 Embryo)をカテーテルを用いて子宮内に移植すること(Embryo Transfer、略してET)を含めて、体外受精・胚移植(IVF-ET)とも言います。
もともとは、両側の卵管が詰まっている場合に適用された方法ですが、その後その他の原因に対しても使われるようになりました。
30年以上前は、成熟した卵子を女性の卵巣から採取する際に、腹腔鏡を使用しましたが、現在は経腟超音波を使って経腟的に採卵します。採卵後、卵子を培養皿に移し、卵子の周りに精子を振りかけて(媒精)、精子が自然に卵子の中に入っていくのを待ちます。受精卵(胚)ができ、順調に分割したら子宮に戻します。体外受精では、卵子1個に対して、10万~20万匹の動いている精子が必要です。
採卵後5~6日間培養し、育った胚を子宮に移植する
正常に受精すると、卵子は翌日には第二前核(卵子の中に、男性由来と女性由来、合わせて2つの核が見られる)と呼ばれる状態になり、そしてその後、分割を繰り返し、2細胞(2日目)、4細胞、8細胞(3日目)となり、細胞がくっついて細胞の区分けが無くなった桑実胚(4日目)、赤ちゃんになる細胞と、胎盤になる細胞が分かれた胚盤胞(5~7日目)へと育っていきます。
当初、胚移植(胚の子宮への移植)は採卵後3日目の8細胞の時期に行われていましたが、現在では、採卵後5~6日間培養し、胚盤胞まで育った胚を、子宮に移植することが多くなってきています。また、採卵したその周期に移植する「新鮮胚移植法」の他、発育した胚を凍結保存し、次周期以降に、ホルモンや子宮内膜の状態を整えてから移植する「凍結胚移植法」があり、凍結胚移植法が、より一般的になっています。