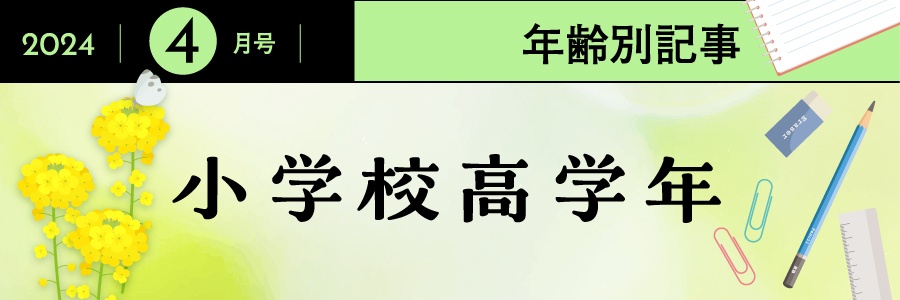「女性が書いた記事は、プロフィール写真が地味だとクリックしてもらえないんです」とあるWEB編集者が言った。「私がどんなに頑張っても、若くて美人の編集者のところにばかり、企画が持ち込まれるんです」とある書籍編集者が言った。「おしゃれにしていないと、女性に話を聞いてもらえないんです」とある弁護士は言った。
3人とも女性だ。意見を言える場所にたどり着くのにも見た目がものを言う、というのは何とも理不尽だが、こうした経験のある人は多いだろう。
誰にも選べない「見た目」の呪縛
見た目はくじ引きだ。自分ではどうにもならない。あたりを引いた人もそうではない人も自分ではどうにもできなかったということにおいては平等だ。あたりを引いたのは手柄ではないし、はずれを引いたのも落ち度ではない。あたりを引いた人がそうでない人から奪ったのでもない。
山を見るにつけても人を見るにつけても、そこに調和のとれた美があるかどうかを無意識に探してしまうのが人の目だ。見たいという欲望はとてつもなく強い。だから人は見た目に振り回される。姿の良いものを見たいという欲望には抗いがたいのだ。同時に、自分を振り回すものへの憎悪もある。自ら見たいと望んだのに、不当に搾取されているような気にもなるのだ。
わが子を「ブス」と言いきり、「だから勉強」と断じたあの母親も、あるいは美人であるがゆえの見た目差別を受けたこともあろう。生まれつき足が速いなら陸上選手を目指せばいいし、顔がいいならそれを強みにして生きればいい。彼女が自分の容姿を活用したのは極めて合理的だ。だけど彼女が、女の美醜を「いい男をつかまえられるかどうか」に直結させてしまうところに、彼女の抱えた抑圧の強さを感じる。