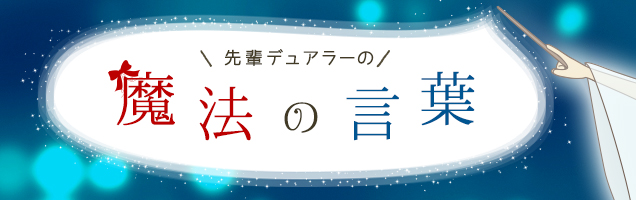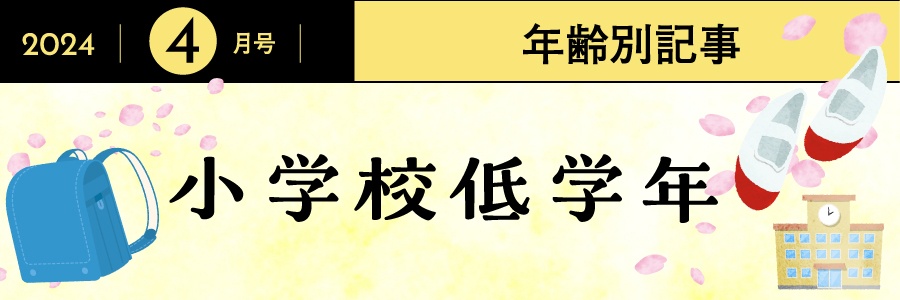妻の足を引っ張ることはしなかった 花マルの“団塊夫”
―― 共働きを続けるというのは、ご夫婦の方針だったのですか。
坂東さん(以下、敬称略) 夫の場合は、応援とまではいきませんが、私の足を引っ張るということはありませんでした。それだけでも、私の世代、つまり団塊の世代の男性としては花マルなんですよ。同世代の男性の多くは、働く奥さんに対して「僕を取るか、仕事を取るか」「子どもはどうするんだ、かわいそうじゃないか」という考えですから。妻が働き続けるのを阻んでしまう男性が多数派だったんですよね。
夫は高校の同級生なので、私のことをよく分かっているんですね。私がアメリカに行くときも、「しょうがないな、行きたいんだろう?」と。「ぜひ行ってこい。君のためにきっとプラスになる」なんていう、絵に描いたようなセリフは聞けませんでしたが(笑)。
当時を振り返ると、同い年の夫もまだ若手で力がなかったのだろうし、お互いに余裕のない状況だったのだから、しょうがなかったんだなと今だから理解できます。自分がいっぱいいっぱいだと、とても誰かを慰めたり、支えたりできないですよね。
―― 子育てにおいて、具体的に実家のお母様にはどのようなかたちでお願いしていたのですか。
坂東 父が亡くなる前は、期間限定でした。「子どもが病気になったから3日ほど来てよ」「1週間ほどいてよ」という感じで頼んでいました。父が亡くなった後は、長く滞在することができるようになり、最終的には同居のかたちになりました。
それまで二重保育の人に保育園に迎えに行ってもらっていましたが、母が行くと子どもがはしゃいで、それはそれは大喜びするんですよ。保育園の先生も「今日はおばあちゃんのお迎えよ、よかったわね」なんて言ってくれて。それを聞いた母は「役に立っている」と実感できて、まんざらでもないわけです。
そのうち、(実家のある)富山に戻ろうとすると、子ども達が「おばあちゃん、帰っちゃダメ!」と引き留めるようになって。母にとっては、それもとてもうれしかったのでしょう。孫の世話が生きがいになっていったのかなと思いますね。そう言って、甘えてばかりいてもいけないのですが(笑)。
次女が生まれたとき、母は72歳だったの。だからとてもじゃないけれど、おんぶはしてあげられない。それでも、小学校に入るまでは何とか生きていたいと言っていたのが、結果的には92歳まで長生きしました。次女の成人式を見ることができて、とても喜んでいました。