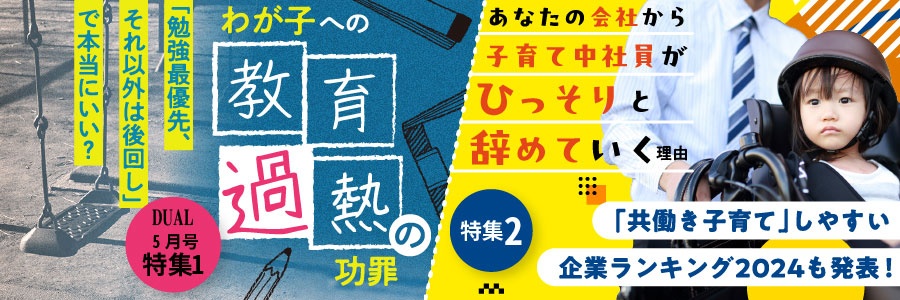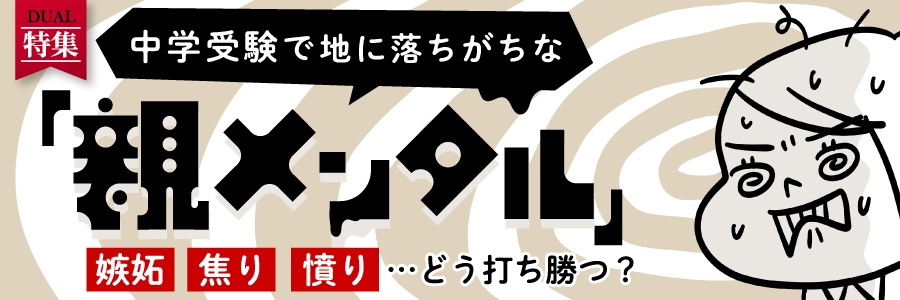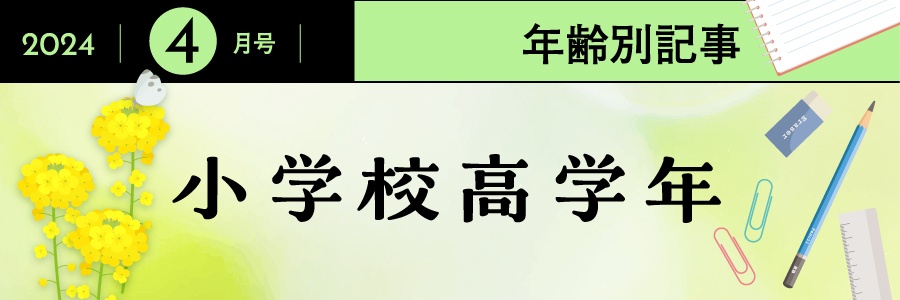「社内に子育て中の社員はいませんか?」と聞くのが第一歩
2014年6月、政府が発表した「日本再興戦略(改訂)」では、「女性の更なる活躍推進」という課題解決策が織り込まれました。このように、働きやすい環境づくりへの取り組みが国や自治体、企業を中心に広がりを見せています。なかでも社内コミュニティーは、職場復帰後の共働き家族にとって身近なテーマといえるでしょう。
ここでいう社内コミュニティ―とは、ランチ会やワークショップなどを通して社員同士が体験や意識を共有し合い、縦横のつながりを深めようというもの。最近の傾向としては、SNSやメーリングリストなどネット環境を活用しながら気軽に関わり合うという人が多いようです。では実際に、どんな風に社内コミュニティーを見つけ出し、つながっていけばいいのでしょうか。また、どんな楽しみ方や可能性があるのでしょうか。
日本アイ・ビー・エム システムズ・エンジニアリング(千葉県千葉市、略称:ISE)の人事部で働く小又茂子さんは、社員にとっての働きやすい環境づくりに長年取り組んできた経験を持ち、社員のメンタルヘルス維持にも詳しいママ社員です。そんな小又さんに、職場復帰後、社内のワーママ&パパネットワークにどう参加すればいいか、またママやパパが心掛けるとよい点を聞きました。
「一番大切なのは、復帰後、自分の状況を周囲に分かってもらうことです。困っていることがあれば、それをできるだけ具体的に話し、素直に『こんなことに悩んでいます。解決策を知りませんか?』と声を上げる。世の中、素直に助けを求める人に真正面から冷たくする人はいません」
「ただ、助け方が分からない人はいるので、『うちの社内に子どもを育てながら働いている人がいたらご紹介いただけませんか?』または、『お子さんが病気になったとき、他の社員の方はどう対応しているのでしょう?』など、気軽に聞いてみるといいですよ」
小又さん自身、現在、大学生と高校生の子ども2人を育てながら働いています。育休を2回取得した後は、会社や保育園、地域など、周りにいるサポーターに何度も助けられたそうです。ポイントは「支え合う関係」でした。
「相手に何かをしてもらうばかりではなく、自分もできることで相手の役に立つという関係が持てるとうまくいくと思います。例えば、私の場合、年の近い子どもを育てる同僚がいたので、週末はお互いの子どもの面倒を見合って、手の空いたほうが自己啓発の学校に通ったりしていました。私が自分と同僚の子ども4 人を水族館に連れていっている間、同僚が社会保険労務士の学校に行くこともありました」
「また、同僚にうちの子どもを預かってもらっている間に、私が産業カウンセラーの学校に通ったこともあります。こんなふうに、『助けて!』『もちろん。私はこんなことをしてあなたを助けられるわ!』と、気軽に言い合える付き合いを構築するのが理想。そのためには、日々の姿勢や話す内容で自分から情報を発信していくことが大事です。あと大事なのは、常に周りへの感謝を忘れないこと」